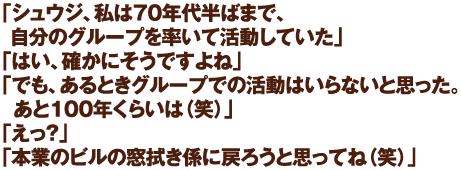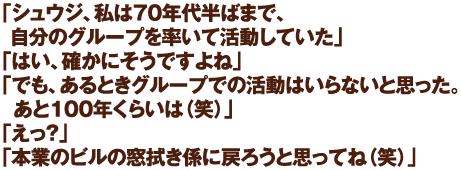
2010年12月、夏のマリーナ・ショウ来日公演への参加に続いて再来日したデヴィッド・T・ウォーカー。12月8日には、DCT recordsからの3枚目となる通算15作目のソロアルバム『For All Time』をリリース、同日から始まった冬のイベント「WINTER FANTASIA 2010 〜DCTgarden "THE LIVE!!!"」への緊急ゲスト参加、そして自身のバンドを率いての大阪と東京での単独ソロ公演、クリスマスの25日には東京・丸ビルでのスペシャルフリーライヴと、約1ヶ月の間、彼の音色に接する多くの機会があった。
前回のこのコーナーでデヴィッド・Tに話を聞いたのが2006年。そのときは、70年代の名作とされるOdeレコード時代の3作品『David T. Walker』『Press On』『On Love』がリイシューされるというビッグニュースがあった。それ以降、彼を取り巻く状況は一変。翌年2007年には単独名義としては初のソロ来日公演が実現、80年代と90年代のソロ作品の相次ぐCD再発とベスト盤のリリース、そして来日公演のDVDリリース。さらに2008年には実に13年ぶりとなるソロアルバム『Thoughts』を、2009年には初のウインターソング・アルバムとなる『Wear My Love』をリリースし、並行して来日公演も毎年果たすなど活動を活発化。2006年の時点からは想像もできないほど、新たなファン層も獲得しながら、デヴィッド・Tの周辺はひと際大きな盛り上がりを見せた。
そのおかげで、2007年以降、来日のたびに会って話す機会も多くなり、コミュニケーションの回数も自然と増えていった。しかし、滞在期間は限られているため、雑談程度はあるものの、まとまった時間をとる余裕もなかなかなく、きちんとした話を聞くこともなかった。そんな中、新作『For All Time』の素晴らしい仕上がりに感激もした今年、1ヶ月という滞在期間の合間を縫う形で、じっくりと話を聞く機会を作ることができたのだった。
同席いただいたのは、大のデヴィッド・Tファンであり、多くの面で彼をサポートし続けているKadowaki Mayuさん。通訳の役割もお願いしながら、話をしやすい場をつくるのに大きくお力添えをいただいた。この場を借りてあらためて感謝を申し上げたい。
そんなこんなで始まったインタビュー。最新作『For All Time』についてが主題だったが、話はいろいろと広がっていった。

通算15作目となるソロアルバム『For All Time』は、カヴァー曲とオリジナル曲がバランスよく配置されている。特にカヴァー曲については選曲のポイントが気になるところ。まずはその辺りのところから話をうかがうことにした。
|

|
|
DCT recordsからの3作目、通算15枚目のソロアルバム『For All Time』
|
|

|
|
「Going Up!」収録の2ndソロアルバム『Going Up!』
|
|

|
|
「Eleanor Rigby」のカヴァーでデヴィッド・Tが参加しているジョン・レノンのトリビュートアルバム『Love - John Lennon Forever』
|
カヴァー曲の一曲目はビートルズの「Eleanor Rigby」。過去の来日公演でプレイされた彼のオリジナル曲「Going Up」の中盤あたりではこの曲のメインフレーズを遊び心たっぷりにサラリと挿入したり、それ以外にも過去には、1991年にリリースされたジョン・レノンのトリビュートアルバム『Love - John Lennon Forever』収録のカヴァーでもギター参加したりなど、デヴィッド・Tにとってお気に入りの一曲だ。アレンジは異なるものの、原曲同様にストリングスをフィーチャーした今回のカヴァーは、聴き応え十分に仕上がっている。
「“Going Up”はEマイナー、“Eleanor Rigby”はB♭マイナー。キーは違うけどどちらもマイナーキー。曲のアクセントとしてはちょうどいいかなと思ってライヴでは“Going Up”の途中に“Eleanor Rigby”のフレーズを少しだけ取り入れてプレイしてる。ビートルズの曲だし大抵みんな知ってると思うし、フレーズを弾いただけで、リズムの取り方もみんななんとなくわかるだろうと思ってね」
それ以外にもデヴィッド・Tはビートルズのカヴァーをソロアルバムやセッションワークでも時々試みている。直接の接点はあまりなかったそうだが、驚きだったのは、彼がキンフォークス(The Kinfolks)というバンドを組んで活動していた60年代はじめに、ビートルズが彼らの演奏を観に来たというエピソードだ。
「当時、私はキンフォークスというバンドでニューヨークを中心に活動していた。1963年頃、フロリダ州のマイアミにあるペパーミント・ラウンジという有名なクラブで、2〜3ヶ月ハウスバンドとして滞在する機会があった。そこに私たちのバンドのことを聞きつけた彼らはわざわざ観に来てくれたんだ。まだ彼らの活動初期の頃で、ビッグスターになる前だった。だから後から知らされるまで実は彼らが誰だかよくわからなかった。たぶんみんな年齢も同じくらいだったはずだ。そのクラブでは一日4セットくらい演奏していたんだけど、ビートルズの連中はずっと聴いてくれていた。で、クラブの閉店後に、彼らと話をしたんだ」
ビートルズが駆けつけたという、デヴィッド・Tのキャリアを語る上で不可欠なキンフォークスというバンド。その正体は実はあまり知られてない。デヴィッド・Tが最初に書いたオリジナル曲「Recipe」は、このバンド名義でシングル盤としてリリース、その後80年代のソロ作品『With A Smile』でリメイクもされた。
「キンフォークスは私にとってとても重要なバンド。メンバー皆、きちんとしたレッスンを受けた訳ではなかったし、ラジオやレコードを聴いてみんなで学んでいっしょに成長していった。あるとき、メンバーの中で、誰がベースで誰がギターを担当するか、といった話をしたことがあった。私は他のメンバーより1曲だけ多く弾くことができた。だから私がギターをやることになったんだ。その1曲というのはアーニー・フリーマンの“Jivin' Around”という曲だったかな。そのときギタリストの座を争っていたのがトレーシー・ライト。私がギターを弾くことになったので彼はベースを担当することになった。新しくベースを用意するお金もなかったので、彼はしばらくギターにベースの弦を張ってプレイしていたよ(笑)。彼がもし私より一曲でも多くギターで弾けていたら、私はベーシストになってたかもしれないね(笑)」
デヴィッド・Tがソロ活動を開始する1968年直前までキンフォークスは活動。メンバーも多少出入りがあったり複数のメンバーが関与していたり少々複雑ではあるのだが、初期のデヴィッド・Tの活動には欠かせないメンバーが揃っていたことは間違いない。
「自分でいうのもなんだけど、その頃は自分たちが世界で一番すごいバンドだと思っていた。だからビートルズのことなんてあまり考えてなかったんだろうね(笑)。でもバンドをずっと続けていくということはなかなか難しい。成功体験のようなことも必要だし、経済的な問題もある。結局、キンフォークスは1967年に解散。その後、私は1968年にソロアルバムを出すことになって、ベースのトレーシーと、ドラムのメル・ブラウンを誘ってトリオのバンドを組んだんだ。彼らとはその後も関係は続いたよ。キンフォークスの初代ドラマーのアルヴィン・エドモンドは3rdアルバム『Plum Happy』に参加してもらったりしたね」
キンフォークス解散後は、デヴィッド・Tは自身のトリオバンドとして彼らを起用。このトリオバンドは1970年くらいまではメンバーに入れ替わりがあったものの活動を続けていたようだ。メンバーがキンフォークスの面々だったために、このトリオバンドのこともキンフォークスとして扱われるようなこともあったようだが、デヴィッド・Tはあくまでもキンフォークスではなく自身のバンドとして活動していたという。思わず話がキンフォークスの話題に及んでしまったが、この新作がデヴィッド・Tのキャリアを総括するという意味でも、制作過程では当時のことが彼の脳裏をよぎったに違いない。
次にスライ&ザ・ファミリー・ストーンの「If You Want Me To Stay」について。これまでもスライの曲をカヴァーしてきたデヴィッド・Tだが、スライとの接点はどのあたりにあったのだろうか。
|

|
|
「If You Want Me To Stay」のオリジナルが収録されているSly & The Family Stone『Fresh』('73)。デヴィッド・Tお気に入りの「In Time」も収録。
|
「スライはずっと好きなアーティストだ。彼は詩人だし、彼の曲をまた何か演りたいとずっと思っていた。この曲はシンプルでとても弾きやすいということもあった。その昔、スライとビリー・プレストンとボビー・ウォマック、そして私の4人でセッションをしたこともあった。全員ギターを弾いてね。レコーディングではなかったんだけど、たまたま4人が集まる機会があった。70年代は特に何か計画したわけでなくて、みんなが集まってセッションするという機会も多かったんだよ」
これまでも4thアルバム『David T. Walker』収録の「Hot Fun In The Summertime」や6thアルバム『On Love』収録の「I Get High On You」など、スライの楽曲をカヴァーしているデヴィッド・T。ほかにも、5thアルバム『Press On』収録のビートルズナンバー「With A Little Help From My Friends」カヴァーのエンディングで、スライの「Sing A Simple Song」のメインフレーズを使っていることも印象的なアイデアだ。
「“Sing A Simple Song”のフレーズは曲を終わらせるのにとても効果的なんだ。ライヴのときは“Walk On By”の演奏の最後でも同じようなアレンジでこの曲のフレーズを使っている。他にもスライの曲は好きな曲が多いね。“In Time”とかね。彼のプレイはほとんど全部好きだ。そういえば、スライの家に遊びに行ったとき孔雀がいてびっくりしたことを思い出したよ。やっぱり彼はファンキーだとあらためて思ったね(笑)」
今回の新作は、マリーナ・ショウのゲスト参加というのも大きな話題の一つになっている。彼女の名盤『Who Is This Bitch, Anyway?』をコンセプトにしたリユニオンバンドによる2009年と2010年の来日公演で久しぶりに共演をはたしたデヴィッド・Tとマリーナ・ショウ。息の合った素晴らしいステージは、デヴィッド・Tも満足のいくパフォーマンスだったということもあり、新作への彼女の参加が実現した。
「“God Bless The Child”は昔から大好きな曲。マリーナ・ショウに歌ってもらいたくて選んだんだ。同じくマリーナに歌ってもらったアル・グリーンの“Let's Stay Together”も好きな曲。歌詞の内容がとても好きなんだ」
アル・グリーンとデヴィッド・T。実はこれまで共演歴はありそうでない。何か接点があったのかどうかが興味深いところだった。
「彼とはこれまでいっしょにプレイしたこともなければ会ったこともないんだ。最初はこの曲は歌なしで考えていた。でもレコーディング前にマリーナと話をしていくうちに考えが変わった。この曲は女性のシンガーが歌うことが少ないと思ったこともあって、マリーナに歌ってもらうことにした。いいアイデアだと思ったんだ」
名盤『Who Is This Bitch, Anyway?』でのプレイの素晴らしさも手伝って、彼女とデヴィッド・Tのパフォーマンスはいつも伝説のように語られる。デヴィッド・Tいわく、彼女の持つユーモアの感覚が場を和ませ、周囲にもいい影響を与えることができるという。そのことをとても重要だと考えるデヴィッド・Tにとって、彼女とはきっと相性のいいコンビなのだろう。
「マリーナとは『Who Is....』録音以前に会っていたかもしれないけど、あまり憶えてないなあ。『Who Is....』のときは、マリーナも含めてハーヴィー・メイソン、チャック・レイニー、ラリー・カールトン、ラリー・ナッシュ、キング・エリソンなどなど、参加メンバー全員が一緒にレコーディングした。もう一人、ギタリストとしてデニス・バドマイアーが参加していたけど、他の仕事ではあまり接点がなかった。ラリーやデニスはその頃テレビや映画の仕事が多かったように思う。ソウルミュージックの仕事はあまりやってなかったんじゃないかな。その頃に比べると、80年代や90年代はレコーディングで皆が同時に演奏することは徐々に少なくなっていったし、今ではもうそんなレコーディング方法はほとんど無くなってしまった。でも70年代はまだそういうやり方が残っていたね」
次にホレス・シルヴァーの名曲「Song For My Father」について。ホレス・シルヴァーをずっと尊敬しているというデヴィッド・Tだが、彼との接点はどのあたりにあるのだろうか。
|

|
|
「Song For My Father」のオリジナルが収録されたHorace Silver『Song For My Father』('65)。
|
「私が高校生の頃は、彼は凄く人気があって、キンフォークスのときも彼の曲をよく演っていた。“Silver's Serenade”とかね。彼のソングライティングは有名だったし、とても好きだった。中でも“Song For My Father”はとても好きな曲だったから選んだ。元々歌詞がなかったんけど後から歌詞が付いた曲でもある。もう10年以上前、フランスで彼がディー・ディー・ブリッジウォーターとライヴをしたという話をきいたことがあって、そのときに彼女はこの曲を歌った。でも最近は彼はもうほとんど活動をしてないと思う。まだ会ったことはない一人なんだけどね」
また、この曲にはドラマーのンドゥグ・チャンスラーがヴィブラフォンで参加している。
「彼がヴィブラフォンを叩くということは、ほとんどの人が知らなかったと思う。でも私は知っていた。彼は自分のグループで演奏するときはドラムではなくて、他の楽器をやったりするんだ。ドラマーというのはなかなか前面に出る機会がないし、そのチャンスということもあって今回彼にヴィブラフォンを叩いてもらった。メロディ楽器を弾くことで、アーティストとして普段とは違った面を見せることもできる。彼にとっても良い機会だし、アルバム全体としても良い形になると思ったんだ」
いまやデヴィッド・T・バンドの一員として欠かせないンドゥグ。「どこまでもついていく」と発言するほど、デヴィッド・Tへのリスペクトは深い。確かな信頼に裏打ちされた関係の源泉となったのは、デヴィッド・Tのプレイにはもちろんのこと、グループとして共に活動することへの細やかな配慮や真摯な心持ちに対する敬意もあるはずだ。
「1975年くらいまでは自分のグループという形はあった。でも、それ以降は自分のグループはいらないと思った。あと100年くらいは不要だとね(笑)。本業のビルの窓拭き係に戻ろうと思ったんだ(笑)」
もちろんこれは彼一流のジョーク。真面目な表情で突然そんな冗談を口にするので、聞き手としては思わず「えっ?」と慌ててしまう。でも、この呼吸と間合いもデヴィッド・Tならではなのだ。
「でも自分のグループではない形でも、ライヴではバンドメンバーとしていろんなアーティストといっしょにプレイしたよ。クルセイダーズやルー・ロウルズ、アレサ・フランクリン。75年から76年頃にはビル・ウィザースともいっしょにライヴを演っていたし、77年にはカナダのモントリオールにも彼といっしょにツアーを廻った。ほかには、ポインター・シスターズ、フィリス・ハイマンらともやったし、マリーナ・ショウも一日だけだけど以前演ったことがある。そして今はこのバンドにとても満足している。素晴らしいメンバーだからね」

続いてオリジナル曲について。デヴィッド・Tのオリジナル曲は、必ずと言っていいほどその特徴的なタイトルにシンプルに想いが注がれている。聴き手はその言葉からイメージされるフィーリングを、奏でられる柔らかな音楽とともにただひたすら感じればいいし、それ以上のものを望む必要はないのかもしれない。とはいえ、そこは哲学的で深遠さ極まるデヴィッド・Tのこと。言葉の使い方一つとっても、いろいろと深読みしたくなるような個性が毎回溢れており、新作においてもそれは同様の感触がある。
特に今回はアルバムのライナーノーツにデヴィッド・T自身による楽曲へのコメントが寄せられており、そこからも十分に彼の想いは伝わってくる。だが、幾つかの点においてもう少しその想いを感じ取ってみたくて話を聞いてみることにした。
まずはアルバム冒頭に収められた「For All Time Overture」。これまで彼の音楽に接してきた人なら、タイトルに“Overture(=序曲)”というワードを添えたこの短い楽曲を聴いた瞬間、彼がこれまで奏でてきた数々のフレーズがちりばめられていることに気がつくだろう。パッと聴いた限りでも、例えば、マーヴィン・ゲイ「What's Going On」、アルバム『On Love』収録の「Feeling, Feeling」や「Lovin' You」、バリー・ホワイト「Love's Theme」、ボビー・ウォマック「If You Think You're Lonely Now」などのフレーズが重層的に奏でられていることがわかる。
「この曲をレコーディングした時点では自分の頭の中にいくつかのフレーズがあって弾いたことを憶えているけど、今となってはどんなフレーズを弾いたか正確には憶えてないんだ(笑)。他にもアニタ・ベーカーの“Angel”のフレーズも弾いたかな。イントロ部分はマーヴィン・ゲイの“You Sure Love To Ball”でのフレーズだ。ジョニー・エースの“Forever My Darling”のフレーズなんかもあるんだよ」
デヴィッド・Tのライヴでは、曲の冒頭部分にその曲とは違う曲のフレーズを少しだけ挿入するような演出が時折り見受けられる。彼の場合、奏でるフレーズが特徴的であるがゆえ、何気無く弾いたフレーズでも、何か意味があるのではないかと勘ぐってしまうのだ。
「その通り、大抵の場合はそこで奏でるフレーズはメインとなる楽曲と関係している場合が多い。でも、絵画を鑑賞するときもそうだと思うけど、それがなんの絵であるかが重要なのではなくて、そこから得られた印象や感覚を自分自身が感じとることが大事なんだ。つまり、楽曲のフレーズをそのまま奏でるということではなく、その楽曲の持つフィーリングをプレイするという感覚だ。フレーズそのまま正確に奏でているわけではないから、それが何の曲のフレーズかをきちんと聴き取ることは難しいかもしれないね」
フィーリングをプレイする。彼の中に潜むそのフィーリングは、その時々で姿をかえながら常に居座っている。その集積が彼の音楽キャリアそのものであり、これから始まるアルバムの楽曲群にもその意識が注がれているという予感を、この序曲は十分に物語っている。アルバム冒頭として期待感十分な演出だ。
続いて「Compassionate Tranquility」について。「Compassionate」と「Tranquility」という言葉は、日本人には馴染みが薄い言葉ようにも思えるため、その意味を理解することが難しいようにも感じるのだが。
|

|
|
「Feeling, Feeling」収録の6thソロアルバム『On Love』('76)
|
|

|
|
「Time Of Stillness」収録の11thソロアルバム『Dream Catcher』('94)
|
「モノや人への想いを綴った曲だね。イメージとしてはアルバム『On Love』で演った“Feeling, Feeling”と同じようなものだ。“Tranquility”というのは“Peacefullness(=静けさ)”という言葉に置き換えてもいい。ソロアルバム『Dream Catcher』で演った“Time Of Stillness”とも感覚は似ている。そういうイメージを合わせ持ったような意味だ。“Compassionate”と“Tranquility”という言葉を同時に使うことは普通はあまりないんだけど、これは私の造語のようなもの。同じ意味のことをさまざまに表現できるけど、この曲のタイトルは私らしいスタイルの表現になってると思う。大きな意味ではやはり“愛”がテーマなんだよ」
“静寂”や“平穏”。おだやかな心持ちの中に存在する“愛”。そのせいか、ストリングスによる荘厳な世界の中に、楽曲中盤にはバリー・ホワイト&ラヴ・アンリミテッド・オーケストラの「Love's Theme(愛のテーマ)」のフレーズがサラリと挿入されてもいる。
「“Tranquility”から“Peacefullness”の境地に達するのに自分にとって必要なのはユーモア。“Love's Theme”のフレーズを挿入したのも、自分なりのユーモアの表現なんだ。ユーモアというのは自分にとってはリラクゼーションの一つでもあるからね」
ユーモアを大事にする感覚を自身の作品に常に投影し続けているデヴィッド・Tならではの表現方法。おだやかで柔らかな表情で佇む楽曲に瞬間キュートでハッとさせられるポイントを加えた彼一流のアイデアだ。
続いてのオリジナル曲は「Justified」。この言葉も実に深い言葉。日本語に訳してピタリとハマる言葉がなかなか見当たらない。
「もともとこの曲は“Justified, Satisfied, Glorified”という、3つのワードを並べたタイトルを考えていた。どの言葉も同じような意味を持つけど微妙に異なるニュアンスがある。“Satisfied”は、満ち足りているという意味だし、“Glorified”という言葉は“神がかっている”とか“神聖な”というような、少し精神世界のようなイメージがあって言葉の意味が若干強くなってしまう。3つの言葉を連ねると少しトゥー・マッチな感じもした。だから“Justified”という言葉のみをタイトルにした。“Justified”は言い換えると“It's OK (=大丈夫)”ということ。多くを望むでもなく、今の状況に満足していることを受け入れることを善しとしてもいいんだよ、ということだ。Satisfied、Glorified、Justified。この3つの言葉を並べてみると、その意味がなんとなくわかるんじゃないかな」
今回の来日公演のステージでも披露されたこの曲。ゆったりと粘り気たっぷりに奏でるリズム&ブルースは、久しぶりに使用したワウワウ・ペダルによる多彩な演出も加えながら、デヴィッド・Tのルーツを感じさせるに十分な躍動感に満ちている。
続いては、実に「Press On」以来、彼が真正面から歌にこだわって表現した「Joyful Insight」。ギタリストがギターを通してメッセージを込めるのと合わせて、「うた」という表現手段を敢えて使ったことの重要性をあらためて感じてしまう一曲だ。
「誰かから何か言葉を受け取ったとき、例えばグリーティングカードでも何でもいいんだけど、そこに記された言葉というのはそれを贈った人の“心”から溢れ出たものであって、それを受け取るということは、その人にとっての喜びのはず。“Insight”は、言い換えると“Understanding (=理解)”ということ。受け取ったことこそが喜びになる。そんな意味だね」
この曲の歌詞にギターのくだりがある。“I am now going to let my guitar speak for me(私は今、ギターに語らせようとしている)“、そして、“Now the guitar is my voice(ギターは私の声だ)”。これこそデヴィッド・T・ウォーカーというギタリストの本質を突いた、いや、彼の音楽表現のすべてが注がれた言葉だと言ってもいいはずだ。ギターを通して語ったことが相手に伝わる、そして受け入れられるということの喜び。そのことをギターを通して語りながら、同時に敢えて文字通り「言葉」を駆使して自ら歌い表現したことに、この曲に寄せる強い感情が伝わってくるのだ。
「“Joyful Insight”という言葉は、言い換えると“Good News (=Some Information)”ということ。自分が知らせたいこと、伝えたいこと。その伝えたいこととは、自分の中にある“愛”について、ということだ。言葉は時として複雑になったり邪魔になったりすることもある。だから私はギターに弾かせて伝えているんだけど、今回はそのことそのものを伝えたかったので、敢えて歌をうたうという形をとってみたんだ」
言葉を使わないアーティストが、言葉を使って表現することの意味と重要性。アルバムに収められた「Soul, In Light & Grace」や「For All Time」でも使われた「うたう」という表現手法が意図した形で注がれているという点で、想いの輪郭は明確に描かれた。
「“Joyful Insight”は実は当初は歌うつもりはなかったんだ。でも途中から気が変わった。それで、トラックのレコーディング作業は全部終わっていたんだけど、ミュージシャンたちが誰もいないスタジオで一人で歌った。だから他のミュージシャンたちは完成するまでこの曲に歌が入ってることを知らなかったんだ。そういう意味では“Press On”の録音のときと似ている。この曲や“Soul, In Light & Grace”もそうだけど、そういう意味では“Press On”の続編のような意味合いもあるかな」
|

|
|
「Press On」収録の5thソロアルバム『Press On』('73)
|
|

|
|
「Watts At Sunrise」収録の8thソロアルバム『With A Smile』('88)
|
そしてその「Soul, In Light & Grace」。同じくデヴィッド・Tがヴォーカルを担ったこの曲を聴いたとき、感覚的にまさに「Press On」と相通じるニュアンスとテイストを体中で感じたのだった。一つにはこの曲のイントロ部分に、かつて彼のソロアルバム『With A Smile』に収録された「Watts At Sunrise」のイントロフレーズが使われているからだ。このフレーズはライヴでよく彼が奏でるフレーズでもある。さらには「Watts At Sunrise」のイントロ部分には「Press On」のイントロフレーズが丸ごと使われているという繋がりもある。
「あのフレーズは、私の父がよく弾いていたフレーズなんだ。決して簡単なフレーズではないんだけど、なぜか父はこのフレーズをよく弾いていた。私は幼い頃、父が奏でるそのフレーズをよく聴いていた。だから自然と憶えたフレーズなんだよ」
そのフレーズを「Press On」のフレーズとともにイントロに使った「Watts At Sunrise」という一曲。さらにそのフレーズを「Soul, In Light & Grace」にも使ったという点で、この3曲に特別な繋がりのようなものを感じたのだ。
「“Watts At Sunrise”に“Press On”のフレーズを使ったのは意図的だったんだ。私が育ったワッツというところは貧困層の街だった。普通だったら“Sunrise”という言葉は美しいものの象徴だったりするんだけど、ワッツではそうではなかった。だから“Press On”のフレーズを使うことで、そういう境遇から前向きに進もうという気持ちを表現したかった。それが逆にユーモアとして表現できるとも考えた。ワッツの朝日は決して美しくはないのかもしれないけど、プレスオンの精神で進めばいいんだ、ってね」
また、この曲には彼が常々表明する「Press On」や「With A Smile」などのキーワードが彼の口から発せられる言葉として随所で歌われている。歌詞カードにはそれが「アドリブ」と記載されている。
「そう、まさにアドリブだった。メインテーマの“Soul, In Light & Grace”の歌詞の部分はみんなでコーラスをやって、そのあとは私一人でアドリブで歌った。今回のメンバーは私を含めて普段はあまり歌わない人たちばかり。だからみんなでコーラスをやることで、パーティのような感じでレコーディングを盛り上げることができるかなとも思ったんだ。プロのシンガーだったら完璧すぎてあまり面白くない。この曲に関してはプロのシンガーじゃないみんなが歌うことを大切に考えたんだ」
まさに一つのチャレンジ。この曲は、2010年の来日公演のステージでもアルバムと同様にメンバー全員によるバックコーラスとデヴィッド・Tのアドリブによるヴォーカルが披露された。ステージ上では滅多に歌うことのなかったデヴィッド・Tの、これもまた一つのチャレンジ。“プレスオン”の精神がここにも注がれているのだ。
そして、ラストを飾る「For All Time」。アルバムタイトルにもなっていることから、この言葉に込められた想いは特別なものなんだという想像はあった。日本語に訳すと「いつも、ずっと、いつまでも」という意味になるというこのタイトル。歌われた歌詞世界からもパーソナルなイメージが喚起される。同時に、聴き手の誰もがこの言葉を自分自身の心持ちで解釈できる普遍的なテーマでもあると感じるのだ。
「最初にこの曲を作ったときには、私自身のとてもパーソナルな歌だった。でも作り終えた今となっては、誰のものでもなく、みんなのもの。この歌のグルーヴやメロウネスはみんなのためにあると思ってほしいね。この曲も、そして“Joyfull Insight”も“Soul, In Light & Grace”もそうだけど、いずれも歌詞は短くて、曲の中で語られている物語が完結していないように見えるかもしれない。でも、その短い歌詞の中で自分が言いたかったことは全て表現している。だから、例え言葉がどんなに少なくても、それぞれの曲の物語はその曲の中で完結しているんだ」
多くの言葉で語らないデヴィッド・Tらしい表現方法がここにある。饒舌である必要はない。少ない言葉だからこそ、そこに込められたスピリットが美しく響き渡るギターの音色と融合することで、彼の描く物語は普遍的なメッセージとなってどんな聴き手にも届く。「いつも、ずっと、いつまでも」の想いは振り返るとアルバム全編に込められたメッセージ。そして彼の音楽そのものも“For All Time”な心持ちで存在するということ。それはライナーノーツに記された彼自身による楽曲解説に、彼が作った数々のオリジナル曲のタイトルが文章としてちりばめられていることからもわかる。
「そうだね。曲の中にいろんなフレーズをちりばめたりするのと同じで、解説の中にもそういう手法を使ってみたんだ。そうすることで曲の意味合いがより明確になったりするんじゃないかと考えた。私の曲のことを知らない人にとってはただの言葉かもしれない。それはそれで文字通りの言葉として普通に読み取ってもらえればいいし、知っている人にとっては私の世界がより伝わるんじゃないかなとも思ったんだ。アルバムのタイトルでもある“いつまでも”という意味は、私の作った楽曲についても言いたかったこと。アルバムには私が書いた曲ではない曲もあるけど、それらの曲も含めて“いつまでも”ということを込めたつもりだ」

新作『For All TIme』のリリース元であるDCT recordsからのインフォメーションには「3部作完結編」とある。アルバム全体に彼のキャリアを総括するようなニュアンスがちりばめられていることを考えると、この作品が彼にとって最後のアルバムになるのではないか、という思いも脳裏をよぎるのだが。
「今の段階ではまだ何もわからない。これまで私のソロアルバムは各年代で3枚ずつ作るというパターンがあることをみんな知ってるから、そう思われているのかもしれない。いろいろとアイデアはあるけど、まだハッキリとしたことは何もわからないな。最後のアルバムになるかどうかなんて誰にもわからない。ジョン・コルトレーンにしてもマーヴィン・ゲイにしても、これで最後と自分で考えて作品を作ることはなかったはずだからね。ただ、作る必要を感じないときは何もしないということだ。なにせ、過去13年間、何もやらなかったこともあるわけだしね(笑)。大切なことは“Press On”そして“With A Smile”ということだ」
そう言って、目の前のジェントルマンは、本気とも冗談ともつかない柔らかな表情で笑った。この新作には彼のキャリアの集大成的なニュアンスが充満している。その意味では今後、彼がこのアルバムを超える、あるいは、新しく表現したいと思えることが明確にならない限り、作品という形が実現することはないのかもしれない。しかし裏を返すと、新しく表現することがあるのなら、彼は喜んでギターを手に取るということだ。
過去の作品から最新作まで、そして数え切れないセッションワークの一つ一つ。決して懐古的な佇まいに終わらず、特徴的な音色で進化を続ける彼の音楽は、今あることをそのまま受け入れ、続けていくことの大切さをいつでも教えてくれる。それは聴き手のピュアな心持ちにシンプルに響く。まもなく70歳を迎えアーティストとしても円熟期真っ只中の巨人が注いだ、こんなにも情熱溢れる音楽表現の粋を僕は他に知らない。落ち着きのあるしっとりとしたハートウォームな佇まいだけでなく、若々しく瑞々しさに満ちたエネルギッシュな躍動が重なる新作には、50年に渡るキャリアを回想しながら常に前に進むというチャレンジの源泉が見え隠れする。それを惜し気もなく変わらぬ音色で届けてくれたこと。それだけで僕は十分だし、感謝以外に言葉はないのだ。
いつかひょっこりと突然に、新たなチャレンジを試みるジェントルマンの姿にまた出会えるその時。「For All Time」という言葉の意味を、優しくも鋭い音色とともに、きっと僕らは思い描くはずだ。
2010年12月 東京都内某所にて
構成・文/ウエヤマシュウジ
Thanks to Mayu Kadowaki
|
|