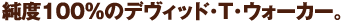── まずは、総合プロデューサーとして新作『Thoughts』の制作に至る経緯をお聞かせいただけますか?
中村正人さん(以下、中村):ずっとデヴィッド・Tの新しいソロアルバムが聴きたくて、これまでいろんなタイミングでデヴィッドにお願いしていたんです。これまでのソロアルバムを含めて、僕はデヴィッドの音楽は全部好きなんですけど、今の彼をしっかりと表現したアルバムを聴きたいなっていう想いがずっとあって。今の彼のプレイをしっかりと記録しておきたかった。それが、僕と吉田がこのアルバムを作りたかった最大の理由です。他に何も目的はなくて。1995年くらいから彼にいろいろと仕事をお願いし始めて、ずっとそう思ってました。13年経って、やっと実現できた、と。
── そのきっかけはなんだったんでしょう?
中村:やっぱり去年(2007年)の来日ツアーが大きかったのかな。それが彼をその気にさせたんでしょうね。DCT recordsは小さなレコード会社なんで、新作が出るとしたら別のところからなのかな、なんて最初は思ってました。彼の新作が出るんだったらうちの会社からでなくてもどこからでもいいと思ってましたから。
── 最終的には中村さんがデヴィッド・Tを説得したわけですね。
中村:今回、デヴィッドと新しいアルバム制作の話をしたとき、最初は僕と二人で作るアルバムと思ってたみたいでね。僕が打ち込みをやって、デヴィッドがギターを弾いてっていう。そんなものを想像していたらしいんですね。
── へえー。そうなんですか。
中村:でも、もし僕がデヴィッドのファンとして聴くんだったら、そんなものは絶対に買わないだろうなって。そんなのイヤだなって思って(笑)。で、自分自身に問いかけたんですよ。どんなデヴィッドのアルバムが聴きたいかって。そしたら、やっぱりデヴィッドが自分でプロデュースするアルバムだなって思ったんです。なので、話が進むにつれて、次第にコンセプトが変わっていったんですね。デヴィッドも「マサトがプロデュースやるんだろ?」って言ってたんだけど、僕も「やっぱりデヴィッドがやってよ」みたいなやりとりがあって。で、ロスに吉田と二人で行ったんです。
── それがドリブログに書かれてたあのときの話ですね。あの記事を読んで、これはもしや!?、と思ったファンの人が結構いたようです。
中村:そうですね(笑)。ま、出来上がるまでは何が起こるかわかりませんから、あんな風な書き方になってしまったんですけどね。で、ロスで一週間。毎日毎日、打ち合わせして。最初はホテルで打ち合わせしてたんだけど、そのうち、デヴィッドの家で打ち合わせやろうってことになって。デヴィッドの自宅でアルバムコンセプトの詰めをやったんです。
── 選曲はどのように?
中村:彼がレコーディングとかライヴで演った曲とか、僕と吉田とデヴィッドでいろいろとアイデアを出していったんです。作りかけのオリジナル曲もあるからっていうことで、じゃあそれも入れようか、とか。僕自身、デヴィッドにやってほしい曲もあったので、それも候補にしながら。僕らが持ってきたものと、デヴィッドが持ってきたもの、全部で40曲近くの候補が並んだんです。
── 最終的にはデヴィッドが決めたんですか?
中村:そうです。デヴィッドの家のキッチンで、選曲会議をしましたよ。
── キッチンで?
中村:そう。食べ物一つない、キレイなキッチンでね(笑)。
── そうか、自宅ですもんね。デヴィッドの。
中村:もうね、気絶しそうになるような部屋があって。彼は、これまでのいろいろなモノを全て残してあるんですよ。初めて手にしたギターとか、もちろん愛用していたバードランドもあるし、彼の歴史の全てがそこにあるんです。
── わー、見てみたい……。
中村:写真を撮るのも忘れるくらいで(笑)。記念に写真を撮っておこうという気にすらならなくてね。教会で写真を撮る気にならないような感覚と似ているというか。神聖な場所というか。ここに来た者だけが見れるみたいなね。そんな気分でしたね。
── 今回のアルバムで、やっぱりこの選曲が素晴らしいと思ったんですが、同時に、これを全部デヴィッドが選んだのかなというのはちょっと疑問だったんですよ。
中村:そういう意味で言うと、今回の選曲について大きかったのは吉田かな。彼女がすごく熱心に考えていて。例えばクルセイダーズの「Street Life」なんかは僕や吉田がずっと推してたし、スティーヴィー・ワンダーの「Ribbon In The Sky」は吉田がずっと推してて。マーヴィン・ゲイの「I Want You」は僕が、とかね。良い意味で3人が曲の候補を出し合って、蓋を開けて並べてみると、バラエティに富んでるし、今一番聴いてみたいな、っていう曲が並んだ感じです。
── すごくいい選曲だと思います。
中村:笑っちゃったのは、選曲会議をしてたら、譜面がでてきちゃうんですよね。
── 譜面が?
中村:これは70年代のあのとき演ったとか、クルセイダーズのライヴで演ったときのだとか、ミーティングしてると、当時使ってた譜面を持ってくるんですよ。セロテープも茶色になってる正真正銘の当時使っていた譜面です。それをずっと大事に保管しているんですよ彼は。キレイに整理して全部持ってるっていうね。
── 几帳面なデヴィッド・Tらしいですね。
中村:キレイ好きで整理好き。何か話題になると「あ、あれは確か……」って言ってすぐにサッと出てくる。これにはホントに笑っちゃった。僕もね、ドリカムの譜面は全部とってあるんですよ。キレイに整理して。だから、この性分はデヴィッドと似てるな、って思いましたね(笑)。
── 昔のことは憶えてないな、なんて言うことも結構多いですけどね。
中村:確かにそういう面もありますけどね。でも、彼は彼自身のアーカイブというのかな、すごく大事にしています。今回のアルバムに使った彼の昔の写真だって全部とってあったんですよ。デヴィッドのお姉さんがキレイなアルバムにしてくれてて。
── 見てみたいなあ〜。
|

|
|
80年代まで彼のプレイを支えたギター“バードランド”。ここ数年は使用されず大事に保管されている。
|
中村:でもね、僕はそれを良く見ることができなかったです。なんかこう、王家の秘宝に触れちゃった、みたいな感じというか。見ちゃうと、もうこの先、僕ダメになっちゃうんじゃないかっていう。僕の人生、もうここで終わっちゃってもいいやっていう気分になっちゃうんじゃないかってね(笑)。あのバードランドを目の前にしたときも、自分の感情を押し殺しましたもん。なにげなく見ておこう、みたいな。
── アルバムに使われていたデヴィッド・Tの赤ちゃんの写真は、かわいいですよねー。
中村:ジャケットのアートワークは吉田のアイデアなんですよ。Odeの3作のような、良き時代を踏襲したようなジャケットにしたいっていうアイデアがまずあって。CDの蓋をあけると、デヴィッドの歴史が流れてるようなね。

── 録音についてはどうでしたか?
中村:最初はアレンジャーどうしよう、コーディネーターどうしようとか、いろいろ考えはあったんだけど、僕が今回やらないってことに決まってからは、デヴィッドが積極的に動いてくれるようになって。「全部オレがやるから安心しろ」ってね。
── 参加したミュージシャンたちもデヴィッド・Tが?
中村:そうですね。去年のツアーメンバーも含めて、彼の旧友たちが揃ってくれて。こちらが用意するコーディネーターがいたりすると、話が難しい方向になっちゃたりするので、デヴィッドがそのあたりを全てまとめてくれたって感じですね。アレンジにも僕は一切関わってないですし。
── そうだったんですか。
中村:最初は僕はオーケストラを使いたかったんですよ。どうしてもストリングスを入れたくて。
── ああ、やっぱりそう思いましたか。
中村:弦楽器の音をシンセサイザーで代用してもデヴィッドのファンのみんなは嫌がるだろうな、って思って。でも、デヴィッドは自らそれを断わったですよ。今回は生ストリングスは無しでいきたいって、そう言うんです。
── へえー。
|

|
|
ジーン・ペイジ。ストリングスアレンジャーとして、あらゆるポピュラーミュージックでその手腕を発揮した天才。60年代から1998年に他界するまで、多くの名演を残し、“ジーン・ペイジの横にデヴィッド・Tあり”と言われるほどの名コンビだった。ラヴ・アンリミテッド・オーケストラ「愛のテーマ」の原曲でもデヴィッド・Tとともに彼がアレンジャーとして参加している。
|
中村:確かに、本格的にストリングスを入れて作ろうとなると、いろいろ考えなきゃいけないこともあります。それこそ僕らのようなデヴィッド・Tファンが求めようとすると、ジーン・ペイジが必要になってくるし。吉田美和の最初のソロアルバム『beauty and harmony』のときに、ジーン・ペイジにお願いしたときにも、どうしても必要なヘッドバイオリニストが2名いて、その二人がいないとダメだと彼に言われたんですよ。70歳を超えてるような二人なんですけど、この二人がラヴ・アンリミテッド・オーケストラの全てなんだと言うんです。久しぶりのレコーディングで久しぶりにバイオリン弾くぞっていう二人で、大丈夫かな〜って感じだったんですけど、一音弾いた瞬間に「これだ〜!」っていう音がそこに出てくるっていう。そういう世界なんですね。
── うーん、なるほど。
中村:僕らデヴィッドのファンは、そういう世界で出来上がった音を今まで聴いてきたわけなんですよ。それを今のプレーヤーに置き換えて録音することはできるけど、それだったら、当時の音を聴けばいいじゃないって思ったんですよ。なにより、デヴィッド自身が今回は生の弦楽器はいらないって言うんですから。生のストリングスを使わなかったことを良しとしたデヴィッドをみんなわかってほしいなと思うんです。彼が妥協してるわけではないんです。それが今の彼なんだって。結果として、この新作に収められた「Love's Theme(愛のテーマ)」で、キーボードで弾いたストリングスの音が、不思議と良く聴こえてくるんですよね。
── 同感です。あれはなんなんでしょうね?
中村:あれもデヴィッド・Tのマジックですよ。機材にしたって特別なものは何もなくって、メンバーみんな普通のものを使ってるんですよ。こっちとしては、エレピとか新しい機材とかもっといろいろ使ってもいいんじゃないの?とか思うわけですよ。でも、彼らは一切お構い無し。そんなことは彼らにとって重要なことじゃないんですよ。今になって思うと、それが逆に良かったなって。
── というと?
中村:コンピュータから流れてくるこの新作の音を聴いて、すごく納得したんですよ不思議なことに。iPodで聴いて楽しいと感じたし、ヘッドフォンで聴いてても楽しい。生のオーケストラのような、ある種オーバーなものは必要ないんだなって思ったんです。
── なるほど。
中村:もちろんそんなことはデヴィッドは意識してなくて作ってくれたんだろうと思うけど、でも結果としてそう感じることが凄いなと思うんです。最終的にはこの「愛のテーマ」という曲は完全に「デヴィッド・Tの愛のテーマ」になってるっていう。ラヴ・アンリミテッド・オーケストラの「愛のテーマ」とは違う、デヴィッドの音楽になってるんですよ。これが凄いな、と。
── 確かに。
中村:僕がミキシングの場に立ち会っていたら、もうとんでもないことになってたかもしれないと思いますよ。ここはもうちょっとこうしようとか、いろいろ言ってしまってたかもしれない。そして、本当の目的を僕自身が見失ってしまってたかもしれない。だから今回、デヴィッドに全てを任せたというか、デヴィッド自身が全てをやったということが本当に良かったと思うんです。最終的には僕らが聴きたかったデヴィッドのアルバムになっているっていう凄さ。
── マジックですねー。
中村:カヴァー曲にしても、カヴァーを演ってもらう、っていう感じになっちゃうと、いろいろと難しいところもあると思うんです。ところが、ここで重要なののは、カヴァー曲がすべて彼のオリジナルのように仕上がってるってことなんですよ。ここで選曲した曲たちは、彼が昔レコーディングやステージで演ってきたり、彼の音楽的なファミリーたちが生み出してきて関わってきた音楽でしょ。それはデヴィッドの歴史そのものだし、それが実にバラエティに富んでるっていう。キーワードはDavid T. Walkerのバラエティ、そしてヒストリーですよね。
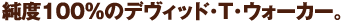
── 出来上がったアルバムを聴いてどういう印象でしたか?
中村:僕はこのアルバムの前で客観的にいようって最初に決心したんです。僕の趣味で出すようなアルバムではいけない。「デヴィッドが好きだからアルバムを出しました」というのではなくてね。それは彼に失礼だと思ったので。これはDCT recordsの方針なんだけど、他のレコード会社ではやらないこと、そして我々にしかできないこと、アーティストを世の中に届けること。その基本方針の中で、デヴィッドのアルバムを出したいと思ったんです。デヴィッド・Tの素晴らしさというのは必ず多くの人に受け入れられるし、コアなファンだけではなくて普通の人たちが毎日の生活の中でどこかでふと彼の音に触れた時に、必ず心に触る音なんですよ。そういう音楽を届けようという考えでこのアルバムを作ったので、僕の中では全く浮かれてないんです。作ったものに対してみんなが評価してくれて、ちゃんと対価を得ていく。そういう積み重ねがとても大切なことだと思ってるんです。だから、すごく冷静です。
── なるほど。
中村:アルバムが出来上がってきたときも、興奮と喜びを押し殺して聴きましたから。作品を客観的に聴いて、よくこんなにいい作品を作ってくれたなって思いました。本当に誠心誠意やってくれたなって。
── あのタッチが見事に表現されてますしね。
中村:つのだひろさんも言ってたけど、コードストローク鳴らしただけでお客さんがワーっと盛り上がるのはデヴィッドだけだって(笑)。でもホントにそうなんだよね。あのタッチ。僕らはそこに惚れてるわけでしょ?
── その通りです(笑)。
中村:レコーディングにもミックスにも立ち会ってないし、僕は何もやってません(笑)。やったのは最初に選曲会議をしただけ。だから、このアルバムは“ピュア・デヴィッド”。今までにもないくらい全部デヴィッド・Tなんですよ。天然果汁100%のデヴィッド・T。濃縮還元じゃなくて、水も入ってないし(笑)。純度100%デヴィッド・T・ウォーカーであると。こんなハートウォームな音楽、他にないですよどこにも。
── かなりのお歳なのに凄いです。
中村:物凄く元気ですよ。いつも自宅ではダイエットというか、エクササイズやってるっていうし、ウォーキングマシンもあるんですよ。チリ一つ落ちてない部屋でね。スーツがズラーっと並んで、靴がピシーっとしててね。ホント、几帳面で、面白い人ですよ。
── ギターもとっても大切に扱いますしね。
|

|
|
David T. Walker『Thoughts』
(2008.11.5)
アルバムジャケットでデヴィッド・Tが弾いてるのが愛用のカラザース製のギター。
|
中村:今回の来日でも愛用のカラザースのギター一本持ってやってきました。バードランドよりも今使ってるこのカラザースのギターほうが期間として長くなってきちゃうんですよこれから。デヴィッドはこのギターを凄く大切に大事にしているし、僕なんか、このギターをずっと見ているんで、逆にバードランドを思い出せなくなってきたっていうか。でもそれでいいのかなって。
── 彼の今の音がこのギターから表現されますからね。
中村:ミュージシャンって、昔は良かったって言われたくないってところがあるんですよ。確かにね、デヴィッドのファンだったら「バードランドの音は良かった」って言いますよ。僕だってそう思うときがある。でも、本人にしてみれば、今の自分も見てよ、っていうか、まだまだ生きてるんだぞって思うこともあるんじゃないかなって思うんです。だから、今回の新作を作るときも「あの時のように」っていうフレーズは一切言わなかったし。だって「あの時」のほうがよければ「あの時の音」を聴けばいいんだもん。せっかくならバードランドでっていう気持ちもわかります。でも、ちょっと我慢して聴いてみてほしい、と思いますね。あの時は良かったとか、先入観無しにね。これが今のデヴィッド・Tだから。装飾なしに、フェイク無しに、ニューアルバムという形で記録できたことが僕はすごくうれしいんです。僕がごちゃごちゃやったり、誰かがいろいろやったりしなくて、デヴィッドが全部をやったこと。ンドゥグだって、あんなドラムプレイ、他では絶対聴けませんよ(笑)。
── 数あるドラマーの中でもデヴィッドがンドゥグを選んでいるってのがデヴィッドらしいな、と思うんですよね。
中村:デヴィッドは摩擦を好まないタイプですからね。丁々発止のプレイ、なんてものは好まないんですよ。ンドゥグだって、結構リズムがいい加減なところもあったりしてね(笑)。でも、ここで聴ける音楽の楽しさったら、たまらないですよね。
── 彼らの信頼関係があってのことなんでしょうね。
中村:リズムが正確じゃなきゃだめっていう風潮はいつから起こったんでしょうかね? だって、正確じゃなくってもいいんだもん。一拍伸ばしたければ伸ばせばいいんですよホントはね。僕がやってるドリカムの音楽にはコンピュータは欠かせないし、デヴィッドの音楽とはまた違うスタイルのものだと思う。でも、デヴィッドが演る音楽ってのもちゃんとあるんですよ。というか、音楽ってそもそもそういうモノでしょう?ってね。音楽ってなんだという問いの答えが、このアルバムの中にあるような気がしてるんです。今回、僕はホントにいろんなことを学びましたね。
── “ソウツ”っていうタイトルも面白いですよね。彼らしいというか。
中村:彼はなかなかのキーワードマンですよね。“プレスオン(Press On = 押し進めろ)”とかもそうですけど、密かな流行語が作れる男ですよ。彼がいつも思考していることが、常にいいキーワードの要素を持ってるというか。精神性とか生き方とかライフスタイルを含めてね。それが面白いなあと思うんですよ。
── それが彼のキャリアの中でずっと表現されているから凄い。
中村:僕らファンってのは、僕らが求めるデヴィッドの音ってそれぞれあると思うんです。でも、それは既にもうこの世にあるものなんですよ。彼の40年のキャリアと歴史の中にね。だから、この新作にあるのは、誰にも触られてないデヴィッド・T・ウォーカーっていう姿なんです。これは今までなかったことだと思うんですよ。
── 多くの人に聴いでもらいたいですよね、この音を。
中村:そうですね。だから“着うた”だってやるんです。やっていいと思うんですよ。ふと聴こえてくる音が気になったらデヴィッドの音だったって世界って全然オッケーだと思うんです。
── そういう気軽さは大事ですよね。
中村:それこそ、昔のモータウンの時代だって、みんな小さなラジオとかで聴いてたんですよ。それがいつからか、オーディオ的にちゃんとした音で聴かなきゃってことになっちゃったところってあるでしょ? でも、そうじゃないでしょ?って。昔のラジオの代わりが今の携帯で、そこから着うたが流れてきてそれを聴くってこと、オッケーなんですよ。特に今の若い人にぜひ聴いてもらいたいし。着うたから流れてくるデヴィッドの曲を聴いて「あ、これカッコいいね」って素直に思ってもらう。デヴィッドのルックス見て「なんか良く知らないけど、あのギターの人、チョー凄い人みたいよ」って感じてもらう。そんなことがきっかけでいいと思うんです。
── デヴィッドも喜んでますしね。
中村:それは彼が本当にオープンな人だからですよね。だからみんなに愛される。喜びも悲しみも、静かに受け止める人ですからね彼は。ワーっと大袈裟に喜びを表現する人でもない。でも、言葉の端々から、彼が喜んでくれていることはわかります。感謝してるって言ってもくれますしね。
── 今回、新作リリース、WINTER FANTASIAへの参加、そして自分のバンドでのライヴツアーと、一連の流れがいい形で実現してるように思います。
中村:そうですね、そういうチャンスがないと、なかなか来てもらえないでしょ彼らに。彼らがいくら来たくてもそういう場がないとね。彼らのような人たちが音楽を続けていける環境とか状況を作っていくというのも、僕自身大切な仕事だと思ってます。
(2008年11月 DCT records本社にて)
デヴィッド・Tの新作はまだか。ここ数年、あちこちからそんな声が聞こえていた。それもそのはず、前作となる『Beloved』をリリースしたのは13年前の1995年。そろそろ、という期待が膨らむには十分すぎる時間が経過していたのだ。
これまで、新作リリースの話がなかったわけではない。幾つかの企画が持ち上がっては消え実現には至らなかった。2004年にはデヴィッド・T本人もやる気十分、準備万端といううれしいニュースまで伝えられた。が、残念ながらあと一歩、条件が整わず話は見送りに。しかし、2006年末に実現したOde時代の名作3枚のリイシューをきっかけに状況は再び好転。2007年には初の単独来日公演、その模様を収録したDVDリリース、80年代と90年代のソロ作の再発、さらに年末には同じ年に二度目の来日も実現し、2008年の今年はベスト盤までもがリリースされるなど、ひと際デヴィッド・T周辺は盛り上がりを見せた。そうなると、新作はまだかの声も現実味を帯びてくる。そんな用意された舞台にあがるかのように出来上がったのが13年ぶりの新作『Thoughts』。実現させたのは、音楽家として情熱の火種を絶えさせることなくデヴィッド・Tをこの13年間、常にサポートし続けたDREAMS COME TRUEの中村正人と吉田美和の二人だった。
単に新しいアルバムを作ればいいという義務的感覚や習慣化したシステムなど、ここにはない。あくまで自然体に、これまでデヴィッド・T自身が描き続け現在進行形で思考する“想い”と周囲の条件や環境が、彼自身納得いく形で結実すること。これが大前提だった。最後のソロ作『Beloved』をリリースした1995年から奇しくも交流が深まるドリカムの二人の熱意と想いに、デヴィッド・T自身の音楽家としての決意が一つになった瞬間、新作はカタチになっていった。そこに謳われた“13年ぶりの”という形容は、そのまま彼ら3人が歩み育んだ時間そのものとなった。
これだけの音楽を共にできる僕ら日本人は幸せな存在なのかもしれない。その幸せを密かに愉しむ喜びはもちろんある。でも、だからこそ、できることなら、彼の今の音楽を広く世界の人に知ってもらいたい。60年代から70年代の激動の時代を渡り歩き、そして現在に至るまでポピュラーミュージックを支えた巨匠が、今、奏でる音楽を知って聴いて、そして感じてほしい。そう願うのはきっと僕だけではないはずだ。
新作は届けられた。音一つで、タッチ一つで心を刺激し感動を生むデヴィッド・Tの音楽は健在だった。しかし、彼はまだまだ前に進もうとしている。あくまで彼のスタイルで。「彼が残した足跡は誰もが認める偉業。その音をもっともっと身近な存在として聴いてほしい」と語る中村氏の言葉の裏に、まだまだ続く終わらないデヴィッド・Tのヒストリーを感じた。“プレスオン”に代表される、彼が常々表明し心に描く“ソウツ”は、次に歩む1ページに描かれる期待をいつも僕に投げかける。新作『Thoughts』のジャケットに描かれたように、彼は今日もギターを抱えてにこやかに笑っている。
(聞き手・文 ウエヤマシュウジ)
|
|