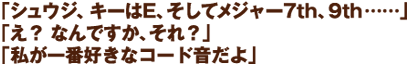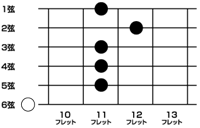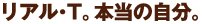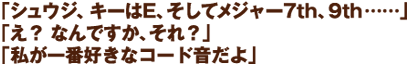
2006年10月、僕はロサンゼルスにやってきた。国内、海外を問わず、出不精の僕にとっては久しぶりの旅行だ。目的は2つあった。一つは、ロサンゼルス在住の音楽プロデューサー、ニール・オダさんに会うこと。もう一つは、3年ぶりにデイヴィッド・Tに再会することだった。
ニール・オダさんは、デイヴィッド・Tの80年代の仕事を数多くサポートしてきた音楽プロデューサー。現在はロサンゼルスに在住しており、数年前からサイトを通じて知り合ったことから交流させていただき、機会があればお会いしたいですね、と話をしていたのだった。
ことの始まりはデイヴィッド・TのOdeソロ3作リイシュー決定のニュースだった。以前からこのCD化問題についてはニールさんともさんざん話をしてきていただけに喜びはひとしおだった。そもそも、このOde3作リイシュー実現の発端の一部は、ニールさんとの会話にあった。
多くの人が名盤と認めるこのOde時代ソロ3作のCD化をレコード会社が放っておくはずはなく、これまでも何度も各社からリイシュー話は企画されていた。が、複雑な諸問題があり今まで一度も実現することはなかった。ニールさんも過去にリイシュー企画の過程に関わっていたこともあり、その事情の一部はご存知だったのだ。障壁となる原因はある程度わかっていたのだが、その壁はどうしようもなく大きく立ちはだかっていた。そんなあるとき、音楽ライターの金澤寿和さんと話す機会があり、偶然にもこのCD化問題の話題になった。金澤さんもこれまで何度か同じような企画をレコード会社と話をされていたということもあって、どうすれば問題点がクリアになるのか二人で思案していたのだった。
その後、金澤さんを通じて日本のレコード会社のビデオアーツ・ミュージックがCD化に名乗りを上げ、交渉に乗り出したという知らせが届いた。結果はOK。そのときの驚きと喜びといったら! タイミングもあったのだろうが、ビデオアーツのスタッフの皆さん、それから金澤さんの尽力には本当に感謝の一言だ。そしてもちろんニールさんにも。皆さんにはあらためてお礼を言いたい。

そんなわけで決定した今回のリイシュー。David Tサイトを運営する立場の僕としても、これは一大ニュースだ。このめでたい話題をなんとか盛り上げたい。ここはやはりデイヴィッド・T本人の話を聞いてみたいという気持ちも沸いてきた。3年前に会ったときは、Ode時代について話をする時間も余裕もなく聞けず終いだったという心残りもあった。そんなことをニールさんとも相談しているうちにふと思いついたのだ。「そうだ、僕がロスに行けばニールさんにもデイヴィッドにも会えるじゃないか」。
気がついたら、仕事のスケジュール調整とロス行きのチケット手配に動き出していた。こういうときの自分はあきれる程に素早い。なんとか日程を調整し、そしてニールさんにも多大なご協力とサポートをいただき、こうしてデイヴィッドとの再会の場を作ることができたのだった。
再会の場所は、ロスのニールさんのご自宅。前日にはニールさんへの取材も終え、一足先に万全の体制でデイヴィッド・Tがやってくるのを待っていた。
そしていよいよ。黒いスーツと黒いシャツに身を包んだデイヴィッド・Tがやってきた。あごヒゲが一層白くなっているような印象を受けた以外は、相変わらずダンディなデイヴィッド・Tの姿が目の前にあった。3年振りの再会だったが、そのオーラと存在感はやはり圧倒的だ。「よく来たね」と笑顔でねぎらいの言葉ももらい、気分は最高潮に達していた。
よく見ると、デイヴィッド・Tはギターケースを2つ抱えていた。実は渡米前にデイヴィッド・Tの愛器であるギター「バードランド」を見せてほしいとお願いしていたのだ。デイヴィッドはその願い通り、一つは最近使用しているカラザース製のニューギターを、もう片方の手にはバードランドを持ってきてくれたのだ!
|

|
|
最近はほとんど手にすることはないという愛器「バードランド」を奏でるデイヴィッド・T。
|
今回リイシューされたOdeレーベルでの最初のアルバム『David T. Walker』のジャケットでデイヴィッド・Tが抱えているギターがバードランド。20年近く文字通り「これ一本」で勝負し、数々の名演を生んだこのギターは、ここ数年はほぼ引退状態に等しく、その姿が表舞台に登場することはない。しかし、Ode時代の話を聞くにあたって、このギターの存在は不可欠だと考えた。無理を承知でお願いし、その願いに応えてくれたデイヴィッド・T。そして、その長年の愛器をケースから取り出し、ポロポロンと奏でた瞬間の凄さ! あの音が目の前で鳴ってる。なんというメロウなトーン! 信じられない!
「5年振りくらいに持ち出してきたよ。チューニングが合ってないかな(笑)」
さらになんと、デイヴィッドは僕にバードランドを預けようとする。え? ホントに? ひゃーどうしよう! どうするどうする? おそるおそる聞いてみる。「触ってもいいですか?」「もちろん」。あのバードランドに触わるなんて! 何をどう弾いてよいのかわからず、とりあえずデイヴィッドにもわかるフレーズをと思い、『On Love』に収録されているミニー・リパートンの「Lovin You」のイントロを弾いてみた。手が震えてるよ。案の上、ミストーン連発。でもデイヴィッドはその旋律をすぐにわかってくれたようだった。苦笑いをしていたのように見えたのは、おそらくたぶん、微笑ましく見守ってくれたということなんだろう。そういうことにしておこう。優しいなあ、デイヴィッド。くぅ〜。
|
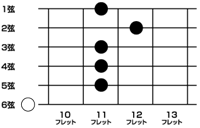
|
|
デイヴィッド・Tがもっとも好きだというコードフォーム。●を押さえ、○は開放。まず6弦を弾き、その後、5弦以下を流れるような感じで弾くと、より艶っぽく奏でられる。 |
バードランドを預け返すと、彼は聞き慣れたあるコード音を奏でた。それが冒頭に記した音階だ。正式なコード名称は本人もよくわからないそうだが(おそらくEメジャーセブンス・ナインス・サーティーンス=Emaj7th9th13thというコード音)、実際は右のようなフォーム。これがデイヴィッド・Tのもっとも好きなコード音だという。ジャズっぽくもあり艶やかなこのコードは、確かに彼のプレイの至るところで出現する代名詞的和音であり、これを元に発展させたフレーズも数々のプレイの中でさまざまに繰り出されている。ハープ音のようなメロウなフレーズはここから出来上がっているわけだ。横から見ると「T」の文字に見えなくもないので、このコードフォームを「デヴィTコード」と勝手に名付けてみた。ジミ・ヘンドリックスが良く使っていたコードを「ジミヘンコード」と呼ぶようにだ。ギターを弾かない人にはなんのこっちゃ?という感じだろうが、もしいつかギターを手にとる機会があったら、このコードポジションを覚えておいて試しに奏でてみてもらいたい。気分はデイヴィッド・Tになること間違いなしだ。
そんなこんなで。興奮と感動のうちに話は始まった。メインの話はOde3部作についてだったが、話はあちこちに飛び火しながら、楽しく進んでいった。昔のことはほとんど忘れていると語っていたデイヴィッドだったが、遠い記憶を紐解きながら、丁寧に一言一言を語ってくれた。
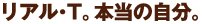
Odeレーベルでの最初のアルバム、彼にとっては4枚目のソロアルバムが『David T. Walker』だ。日本では通称『The Real T.』と呼ばれてもいるこのアルバムは、デイヴィッド・Tにとって、はじめてのメジャーなレーベルとの契約だった。
「私にとっては初めての大きなプロジェクトだった。今になって考えるともっと弾いてみたかったと思うところもあるけど、気分も盛り上がっていたし録音が終わったときは大きな満足感があったね」
きっかけを作ったのは、このレーベルの主宰者でもあり、1950年代から西海岸の音楽業界でソングライターとして活動しながらDunhillレコードの運営にも携わった才人ルー・アドラーだ。Odeレーベル契約以前、デイヴィッド・Tがモータウンのセッションやハリウッドでの仕事もこなしながらトリオバンドとして活動していた頃、とある大学でのライヴステージの観客の一人がルー・アドラーだったことから話は急展開、その場で見初められ、デイヴィッド・TはOdeレーベルと契約する。
「ルー・アドラーはとてもクリエイティヴな人。彼自身がアーティストなんだ。モンタレー・ポップ・フェスティバルでママス&パパスといっしょにやってた人だったから、彼なら安心だと思って契約をOKした。クリエイティヴなタイプの人とだったらどんな人とでもいっしょに仕事ができるんだ」
舞台となったOdeレーベルは、キャロル・キング、ペギー・リプトン、メリー・クレイトン、トム・スコット、ジーン・マクダニエルズといったアーティストが所属していたことでも知られる。配給元であるA&Mレコード所属のカーペンターズやバート・バカラックといったポップアーティストたちとは幾分毛色の異なる個性的なメンバーが顔を揃えていたことでも非常に面白いレーベルだった。
「A&Mの社内報のようなものに自分が一面にでてたんだ。“デイヴィッド・T・ウォーカーと契約した”というようなニュースで自分の写真が掲載されていてね。そのとき初めて、A&Mのような大きなレコード会社と契約できたことを実感したんだ。とてもうれしかったね。それまで私は一般的にはジャズギタリストとして知られていたけど、A&Mはポップレーベルとして有名だった。だからまず最初に言われたのは“ジャズギタリスト”というラベルを剥がしてくれということだった。だからレコード会社からラジオ局などに送られる資料にも、ジャズギタリストという紹介ではなく、ポップインストというような表現を使っていた」
ポップインスト。それまでの肩書きとはその辺りが違っていた。ルー・アドラーはデイヴィッド・Tの幅広い音楽性をいち早く見抜き実践した。その意味で、ルーとの出会いはデイヴィッドにプラスの結果をもたらした。しかし実際のところ、本人は自分がどのようなジャンルのミュージシャンだと思っているのだろう。ある程度予想はしていたが、こんな答えが返ってきた。
「もちろん私はソウルマンなので、自分がジャズギタリストだと考えたことはない。特別にカテゴライズされたりラベルをつけられたりするのは好きじゃないし、自分でもそんなふうに思ったことは一度もない。ジャズであろうがソウルであろうがポップであろうが、なんと言われても別に構わないんだよ」
|

|
|
Peggy Lipton
『Peggy Lipton』('69)
ルー・アドラーのプロデュースによるペギー・リプトン唯一のアルバムにしてソフトロック名盤の誉れ高き一枚。残念ながらデイヴィッド・Tの音色は聴こえてこないが、ペギー自身のオリジナル曲の他、ローラ・ニーロやキャロル・キングのカヴァーなど名曲ずらりの傑作盤。未CD化。
|
|

|
|
Peggy Lipton「Lu」('70)
Ode ZS7-124
上記『Peggy Lipton』には未収録のシングル盤のみのリリース。アレンジャーはジーン・ペイジ。ルー・アドラーの“Lou”の名前に引っ掛けたと思われる選曲であり、彼に捧げた一曲なのかもしれない。
|
|

|
|
Merry Clayton
『Gimme Shelter』('70)
|
|

|
|
『Celebration - The Big Sur Folk Festival 1970』
ビーチ・ボーイズ、ジョーン・バエズといった面々が参加したライヴイベントの録音盤。デイヴィッド・Tは、メリー・クレイトンのバックバンドとして参加。
|
Odeレーベルと契約後、最初の仕事は映画音楽のセッションだった。当時ルー・アドラーが手掛けていたソフトロックグループ「ママス&パパス」のジョン・フィリップスが音楽制作に関わった映画『Myra Breckinridge』や『Brewster McCloud』のサウンドトラックのレコーディングに参加。さらに同じOdeレーベル所属の女優、ペギー・リプトンのソロアルバムのレコーディングにも参加する。
「ペギー・リプトンは当時ルー・アドラーと親しい仲だった。そのせいもあって、彼女の1stアルバムを録音するセッションに呼ばれた。だけどアルバムに収録されているかどうかはわからないんだけど」
ペギー・リプトン唯一のアルバム『Peggy Lipton』からは確かにデイヴィッド・Tの音は聴こえてこない。ただ唯一、アルバムには未収録で同時期にシングル盤としてのみリリースされたローラ・ニーロの名曲カヴァー「Lu」という一曲からは、デイヴィッド・Tらしき音色が僅かに聴こえてくる。今となっては事の真偽はルー・アドラーのみぞ知るということか。
その後、同じOdeレーベルのレーベルメイトのソウルシンガー、メリー・クレイトンの1stソロアルバム『Gimme Shelter』('70)に参加。メリーのバックバンドの一員として、1970年にカリフォルニアで開催された「ビッグ・サー・フォーク・フェスティバル」にも出演。この時の模様を収録したライヴ盤が同じくOdeレーベルから『Celebration - The Big Sur Folk Festival 1970』というタイトルでリリースされ、サイモン&ガーファンクルの名曲「明日に架ける橋」のカヴァーなどで、イントロの数秒間ながらも凄まじくエモーショナルなギタープレイを披露している。
そんな中、1971年に満を持してリリースしたのがソロ通算4作目にあたる『David T. Walker』だ。アルバム中、7曲がカヴァー曲という選曲。バラエティに富んだ実に面白い楽曲が並ぶ。ストリングスやバックボーカルの起用が、歌い奏でるようなギターフレーズと一体化する強烈なブラックネスによって、デイヴィッド・TのOdeソロ作は幕を開ける。
「“Never Can Say Goodbye”は、ジャクソン5でも弾いて好きだった曲。原曲には歌があるから、頭の中では常にその歌詞をうたいながらプレイするんだ。“Hot Fun In The Summertime”は、もともとスライの曲が大好きだったから、どれか一曲演ろうと思っていた。ちょうど夏場のレコーディングだったためこの曲を選んだ。“On Broadway”や“Only Love Can Break Your Heart”は、ルーが持ってきた曲。どちらも気に入っていた曲だった」
どの曲も時代を象徴する印象的な楽曲だが、中でもその代表格的一曲はマーヴィン・ゲイの「What's Going On」のカヴァーだろう。同じくマーヴィン・ゲイが残した74年のオークランドでのライヴアルバム『Live!』や、1993年のバーナード・パーディ率いるソウルジャズユニット「Coolin''n Groovin'」ご一行の日本ツアーでもこの曲をプレイしている。それぞれアレンジは異なるが、本作バージョンは他のどのカヴァーでも聴けないメロウネスと重厚感が特に印象的だ。
|

|
|
4thアルバム
『David T.Walker』('71)
|
「“What's Going On”は、すごく重要な曲だった。この時代に生きていた人が思っていたことをすべて表現した曲だったからね。メロディも気にいっている。このアルバムを録音することが決まって初めてこの曲をプレイしたんだけど、この後も何度もプレイしたね。他にも多くのアーティストがこの曲をカヴァーしてるけど、たぶん私のカヴァーは初期の部類に入ると思う」
こういったカヴァー曲と自身のオリジナル曲の使い分けは面白い。他にもビリー・プレストンが本作のために書き下ろした「I've Never Had The Pleasure」という一曲もある。
「ビリーに何か一曲作ってくれないかと頼んだんだ。それでできた曲がこの曲だ」
|

|
|
71年『David T. Walker』リリース頃のライヴショット。アフロヘアーに縦縞のベルボトム。若き日のアグレッシヴな動きや表情は、年齢を重ね渋い佇まいとなった現在でも、ステージでは時折りその片鱗が垣間みれる。愛すべきギタリストです。
|
デイヴィッド・Tとビリー・プレストンの付き合いは長く、特にビリーのアルバムにはデイヴィッド・Tは数多く参加している。随所で聴けるファンキーなオルガンは、派手さはないもののアルバムの躍動に大きく貢献。セッションでの高揚も想像に難くない。2006年6月に惜しくも他界してしまったビリーだが、奇しくも同じこの年に、本アルバムがリイシューされるというところは実に運命的だ。今回のリイシューはビリーが残していった最後のプレゼントだったのかもしれない。
特徴的なのは、デイヴィッド・Tのオリジナル曲「I Want To Talk To You」と「The Real T.」の2曲だ。特に「The Real T.」は、このアルバムの通称として日本では知られており、またデイヴィッド・T本人もそう呼んでいるほど深い印象を与えるタイトルである。「The Real T.」の「T」は「Truth(=真実)」の意味で、当時「本当のことを言えよ」というスラングとして使われていた言葉だという。
「『T』の一言だけでもその意味は通じていたよ。つまり『Tell the Truth』ってことだ。それに私自身の『T』を掛け合わせたタイトル。このアルバムのことを『The Real T.』と呼ぶのは、この時代の『本当の真実』という想いと、アルバム全体が私自身であるということなんだ。“I Want To Talk To You”という曲は、何事もお互いにしゃべることが大事だ、という想いを込めた曲だし、この2曲に『リアル・T』ということのすべてを凝縮してもいる。“What's Going On”もそうだけど、この時代はさまざまなことがあって、みんなそれぞれ自分の境遇や社会に対していろんなことを考えていた。もっともっとお互いにわかり合おうよ、そんなことを考えながら作った曲なんだ」
生身のデイヴィッド・T。哲学的というと大袈裟だが、この思慮深い発言に単なるギター弾きとは異なるもう一つの彼の姿が見え隠れする。ちなみに、このコーナー「Talk To T.」というタイトルは、彼を象徴する「T」の頭文字の羅列による面白さと、本作に収められたこの「I Want To Talk To You」という曲名から拝借している。「T」は実に奥深い。

続いてはOdeでの2作目『Press On』。アイズレー・ブラザースの「I Got Work To Do」やスティーヴィー・ワンダーの「Superstition」などのヒット性の強い楽曲をはじめとした、ほぼカヴァー曲で占められた構成は前作同様の試みだ。
|

|
|
5thアルバム
『Press On』('73)
|
「ビートルズの“With A Little Help From My Friends”は、トリオでやってた頃からライヴでよく演っていた曲。ヘルプを友達からしてもらうことは必要なことだっていう歌詞がすごく好きなんだ。“Save Your Love For Me”は、20代のときにすごく好きだった曲。車で走っていてラジオから流れてきてあまりに衝撃的だったので車を停めて聴き入ってしまったくらいだよ。ナンシー・ウィルソンもキャノンボール・アダレイもカヴァーしてたし、二人とも大好きなアーティスト。だからどうしても演りたかった曲だった。“If You Let Me”は、 エディ・ケンドリックスの歌でフランク・ウィルソンが書いた曲だけど、もともとこの曲のビートが好きだった。気持ちをもり立てるようなグルーヴがあってとても気に入っていたね。アレンジはジェリー・ピータースだったけど、彼は録音当日、スコアを半分しか書いてこなくて、アレンジが途中で終わっていたんだ。でも演奏中は誰もそのことに気がつかず、みんながスタジオから帰り始めたころに、テープを聴きなおしていたらなんか変だということになって。でもミュージシャンはみんな帰ってしまったから明日もう一回やり直そうってことになってね。ジェリーは天才肌の人なんだけど、ときどきまぬけなことをするんだ(笑)」
この『Press On』というアルバムを語る上で重要なことの一つにキャロル・キングの存在がある。同じOdeレーベルのレーベルメイトということもあり、彼女は本作に収録された彼女自身の楽曲「Brother, Brother」のカヴァーにもバックヴォーカルで参加している。
「当時、私はトライアンフという2人乗りの小さな車に乗っていて、助手席にアンプとギターを積むと人を乗せられなかった。あるとき、仕事が終わって車に乗ろうとしたとき、裸足で歩いてるヒッピー娘が家まで乗っけてってくれない?って言ってきた。誰だか知らなかったし、アンプを移動させるのも嫌だったから断った。でも、後で知ったんだけど、そのヒッピー娘がキャロル・キングだった。彼女が『タペストリー』というアルバムをリリースする前の出来事だ。彼女はその頃すでに“Natural Woman”とか、たくさんの曲を書いていて有名だったけど実際に会ったことはなかったのでどんな人なのか知らなかったんだ。まさかあのキャロルがあんな格好をしてるとは夢にも思わなかった。知ってたら絶対乗せていただろうけどね(笑)」
本作『Press On』には、その直前にリリースされたキャロル・キングのアルバム『Fantasy』とほぼ同じメンバーが録音セッションに顔を揃えている。前作『David T. Walker』と比べて録音参加メンバーに若干の差異が見られるところも興味深いところだ。
|

|
|
Carole King『Fantasy』('73)
|
|

|
|
Carole King
『A Natural Woman ─ The Ode Collection 1968 - 1976』('94)
Odeレーベル時代のベストアルバム。「ファンタジー・ツアー」中のニューヨーク・セントラルパークでのライヴ音源「Believe In Humanity」が収録されている。このライヴでは映像も撮影されたという。うーん、見たい!
|
「キャロル・キングのアルバム『Fantasy』のあと、彼女のライヴツアーに同行した。そのツアーでは、彼女のバックバンドを演るのはもちろん、私は自分のバンドでオープニングアクトもやった。最初に私のバンドが演奏し、バックは同じメンバーのまま続いてメインのキャロルが登場という形式だった。全米ツアーではニューヨークのセントラルパークでも演ったんだ。すごく大きなツアーで、すべてプライベートジェットで廻っていた。ルー・アドラーもいっしょに同行していたんだけど、あるとき飛行機の中でキャロルとしゃべっていて、冗談で『このツアー楽しいからヨーロッパでもやろうよ』って言ったんだ。キャロルはすぐに席を立って、後ろに座っているルーにそのアイデアを持ちかけた。すると翌日にはヨーロッパツアーがブッキングされていたよ(笑)」
各地で盛況だった全米ツアーの中でも、セントラルパークでは10万人という最大級の観客を動員。この頃のキャロル・キングの人気を考えると頷けるが、それにしてもスケールの大きい話だ。そんな中、オープニングアクトとはいえ自身の名前を冠したバンドでパフォーマンスしたデイヴィッド・Tにとっても、その存在感をN.Y.の聴衆に知らしめるには充分な場だった。
「ロンドンではロールスロイスのストレッチリムジンを用意してくれた。で、運転手が『どこに行きます?』って聞いてきたけど、どこも行くところないから適当に街を廻ってくれってお願いして。リムジンに乗った気分をずっと味わいたくってさ(笑)。あと、ライヴのときステージで観客に向かってちょっとしたジョークを言ったんだ。あまりにステージが熱かったんで“まるで太陽の上を歩いているようだ”ってね。で、月面着陸の台詞をもじってジョークにしたんだけど、みんなにからかわれてね。それ以来、ステージではジョークは言わないようにしてるよ(笑)」
『Fantasy』の録音に参加した、ハーヴィー・メイソン(Dr)、チャールズ・ラーキー(B)、ボビー・ホール(Per)、トム・スコット(Sax)らは、ほぼそのまま『Press On』録音メンバーとして起用され、「ファンタジー・ツアー」のバンドメンバーとしても継続された。バンドでの信頼感とアンサンブルの向上が、そのまま自然な形でほぼ同じメンバーでのプレイへと繋がっていったのだろう。
ところで、このアルバムでのキーポイントとなるのは、やはり本作唯一のデイヴィッド・Tのオリジナル曲「Press On」だ。以前、デイヴィッド・Tに会ったときに「Press On」という言葉の意味を聞いたことがあるが、このOdeでの2枚目『Press On』について話を聞くにあたって、そこは避けて通れないと思っていたところでもあった。
「前にも言った通り、“Press On”という言葉にはいろんな意味がある。あるときは“Never Give Up”だったり、あるときは“Keep On Trying”というニュアンスにも使われる。そういうことを伝えたくて、この曲は自分で歌うことにした。この歌詞にこの曲のすべてがあらわされている」
デイヴィッド・Tの数少ない歌声が聴けるのがこの「Press On」という一曲。歌詞はこうだ。
Anytime You believe
In someone or something
and you see
it drags you down
Some acceptance, rebellion and understanding
Will let You
Step away from the pain and
Press On
All there remains to do is to do
just leave worry alone
what you seeing, hearing and doing
Is just the reflection of one mind
Step away from the pain
See yourself and
Press On
「歌詞は日記に書き残したのを覚えている。最近はあまり書かなくなったけど、日記は60年代からずっと書き続けていた。スケジュール帳のようにも使っていたね。今でもすべての日記はキャビネットに入れて全部とってある。ときどき見返したりもしてる。こないだ読みなおしてみると、高校生のときはじめてギグをやったときのギャラが3ドルだったって書いてあったよ(笑)」
僕はこの曲が大好きだ。デイヴィッド・Tの魅力にハマった一曲でもある。イントロのギターフレーズや、小気味良いリズムとグルーヴにしびれまくったのだ。デイヴィッド・Tのライヴステージが実現するとしたら、僕はこの曲を真っ先にリクエストしたいと思っている。
|


|
|
バードランドで「Press On」のイントロを奏でてくれたデイヴィッド・T。アンプを通さず生音だったが、聴こえてくるのはまさに「あの」音だった! 次はぜひアンプを通したバンドアンサンブルの中で聴いてみたい! ちなみに写真下に小さく写ってるのは大好きなポップコーン。
|
「“Press On”という曲は今まで一度もライヴではプレイしたことがないんだ。歌があるからね。歌いながらギターは弾けないんだよ(笑)」
そう言って、彼はおもむろにバードランドを抱え、イントロのフレーズを弾きはじめた。「おおおおお!!!」と狂気乱舞する僕を横目に、「こんな感じだったかな?」とフレーズを確認するデイヴィッド・T。まさにあの音、あのイントロのフレーズ。健在だ!「歌を歌いながら弾けないんだったら、僕ら観客全員で歌いますから。ぜひライヴでこの曲をお願いします!」。そう懇願する僕に、彼は目を細めて笑っていた。
「このアルバムの裏ジャケットは私の祖母が写っている農場の写真なんだ。“プレス・オン”という言葉には、“ずっと続いていく”という意味もある。祖母もこのアルバムを気に入っていたし、だからこのアルバムを聞くと、祖母のことを思い出すこともあるよ。ずっと祖先から続いている歴史の中に自分という人間がいる、つまりファミリーヒストリーだね。昔から続いているもの、そしてこれからも続いていくということ。そういう意味を込めた“プレス・オン”なんだ」
以前、デイヴィッド・Tから聞いた“プレス・オン”の意味は、ポジティヴな意味で使われることが多いということだった。つまり前を向いて行こうというニュアンスだ。だが“プレスオン”には、前を見るという「これから先」の視線だけではなく、「これまで」の視線も常にあるということ。ずっと続いていくもの。その線上に自分という存在がある。その象徴として自身のルーツでもある祖母の農場の写真をアルバムジャケットに使うというセンス。プレス・オン。実に深く、実に粋なソウルマンだ。

Odeレーベルでの3作目『On Love』。アルバム冒頭から、実にゆったりとした美しくも不思議な旋律のオリジナル曲「On Love」が流れた瞬間、前2作とはひと味違う空気に包み込まれる。アルバムジャケット裏面の楽曲クレジット欄にはデイヴィッド・Tの3人の娘、“Davette” “Denise” “Maya”の名前が記されているのも印象的だ。
「“On Love”という曲には、元々、モチーフになった詩があったんだ。その詩がとても好きだったので、曲をつけたらどうなるか、ということで作った曲なんだよ。ただ、その詩に書かれていた内容と、当時の自分自身の状況があまりにも違っていた。離婚問題もあったし、精神的には参っていたときでもあった。でも、自分の子供たちに『結婚という形は壊れてしまったけど、君たちへの愛はこれからも続くんだよ』という気持ちを伝えたかった。この曲はそんな想いを込めた曲だ。バラードで綺麗な曲だけど、ハーモニー的にはちょっと変わった感じの曲。自分でも気に入っている曲だね」
アルバムタイトル通り、キーワードは“Love”だ。とにかくこのアルバムには“Love”が溢れている。
|

|
|
Minnie Riperton『Perfect Angel』('74)
「Lovin' You」「Our Lives」の原曲を収録したミニーの代表的一枚。このアルバムにはデイヴィッド・Tは参加していないが、特に「Lovin' You」はその後も頻繁にプレイすることになる思い入れの深い一曲だ。
|
|

|
|
『On Love』の裏ジャケットに使用された写真の別カット。いっしょに写っている女性は??
|
「“Lovin' You”は、ミニー・リパートンの曲。彼女にはマイヤという娘がいるんだけど、私の3人目の娘も同じマイヤという名前なんだ。同じ名前だっていうこともあって、この曲は子供たちに向けて採り上げた曲だ。元々、この曲はミニーも自身の娘マイヤに対して歌った曲だという共通点もあって、この曲をプレイすることにしたんだ。同じく“Our Lives”もミニーの曲。ファミリーとか友達とか、人と人とのつながりということを自分自身よく考えている。そういう意味でこの曲を選んだ」
特に「Lovin' You」は、その後もチャック・レイニーとの「レイニー・ウォーカー・バンド」でもプレイされ、バンド・オブ・プレジャーでもステージではレパートリーになっていたほど、結びつきの深い曲だ。
「“Windows Of The World”も原曲の詩が好きでね。世界の窓が雨でふさがっている、僕らには太陽が必要だ、特に子供たちには晴れた日が必要なんだ、そんな歌詞がとても好きなんだ。このアルバムの曲は共通してどの曲も詩のイメージがある。愛であったりリレーションシップだったりカンバーセーションだったり、繋がりというような意味で共通するイメージを持っている」
家族、友達、大切な人。自分と関わるさまざまな相手への“Love”。お互いがそれを感じ合うこと。言葉ではなく、自分にとって意志を最大限に表現できるギターという術を駆使した挑戦であり、その想いの切実さが自然な形で伝わってくる。
「“Feeling Feeling”は、他人の気持ちを感じよう、という曲。相手が何をどう感じているのか、思いやりの心が大切だという意味を込めた曲なんだ。もっとお互いを理解しあうようにするためにはお互いを感じあおう、ということなんだ」
アルバムジャケットも印象的だ。このジャケットだけでも一つの話題になるような、いろんなイメージを喚起するデザイン。驚くべきことにこの女性の下半身をモチーフにした写真は、最初、デイヴィッド・T本人が撮ったという。
|

|
|
6thアルバム
『On Love』('76)
|
「マリブの近くにあるプールで、3人の女の子がいたんだ。私はそのときスーツを着てたけど、その女の子たちは何も着てなかった。そのときに私が撮った写真が元になっているんだ。で、A&Mのディレクターがその写真を気に入ってジャケットに使おうよってことになった。でも当時はこういう写真を使うことがいろんな規制もあったのでちょっと危なかった。このアルバムジャケットをセクシーと見るか、花が描かれていることでリスペクトというふうに見るか。どちらがどうということではなく、見る人によって、その人がどんな人かによって、全く受け取り方が違ってくるからね。この時期は自分自身いろんな問題を抱えていてリスキーな時期だったので、裸の女性の下半身をジャケットにするのは多少勇気が必要だった。セクシャルなものなのかリスペクトなものなのか、その意味では差があるジャケットだと思う。自分としては、ピュアな愛というものを表現できるかな、という想いを込めたアルバムジャケットなんだけどね」
いろんな“Love”がある。その想いは自然と他者にも向けられた。同時に自分自身を見つめ直す機会が多かった時期でもあった。前2作にもアレンジャーとして参加したジェリー・ピータースに加え、本アルバムではジーン・ペイジのストリングス・アレンジもより大きく寄与しながら、彼の想いは美しいアンサンブルとなって一つのカタチに結実した。この後、80年代に入るまでソロアルバムは作られなかったことを考えると、このOde3部作の最後を飾るこのアルバムは一つの節目。デイヴィッド・T本人によるプロデュースという点からも、前2作とは微妙に異なるテイストと趣きがこのアルバムにはある。それはとても美しい響きだ。
「以前、ツアーで札幌に行ったとき、『“On Love”をかけると子供がすやすや寝てくれる』という夫婦に会ったことがあるんだ。子守唄に向いてるのかな(笑)」

「今でもこの3枚のアルバムが好きだって言ってくれることはとてもうれしい。正直驚いてもいるんだよ。随分と昔のアルバムだし、私もまだ若かった。でも、この3枚は本当に自分のキャリアの中で大事なアルバムだし重要なものだ。たった5年の間だけど、いろんなことがあったし、自分がその時々に想い描いていたことをそのまま表現したアルバム。そういったアルバムを楽しみに聴いてくれるということだけでもうれしい。リイシューしてくれて、本当に感謝してるよ」
わずかに塩の効いた、ナチュラルテイストのポップコーンを頬張りながら、そして時々ギターをつま弾きながら、にこやかにOde時代の話をしてくれたデイヴィッド・T。彼にとっては遠い遠い記憶の一コマ。「昔の音楽」という表現には、録音から30年以上経った今思うと必ずしも満足いかなかった部分もあったという裏返しも見て取れる。3作通して聴くと微妙に異なるテイストがあることに気がつくし、彼自身が想い描いたテーマのようなものがそれぞれ見えてもくる。本当の自分、ずっと続いていくもの、人を思うこと。「The Real T.」「Press On」「On Love」という3つのキーワードは、あの時代だからこそ想い描けた彼自身の内なるテーマでありながら、実は誰もが抱える最も普遍的なテーマでもある。そのシンプルな想いを究極的な個性を持ったギターの音色で描いた3作。昔も今も、そしてこれから先もずっと、常に居座るその音色だけは間違いなく彼自身であり続けるはずだ。
というわけで、あっという間に時間は過ぎた。別れ際、彼は、日本のファンのみんなによろしくと伝えてくれ、と僕に言った。もちろんです、と僕。そのとき「次は日本で会いましょう」と言いかけて僕はその言葉を呑み込んだ。目の前のジェントルマンのにこやかな細い眼が「きっといつかまた」と語っていたように見えたからだ。瞬間、その表情に若き日のアフロヘアー姿が重なった。30年という時間の変遷によって刻印された年輪の幅は尋常ではない。けれど、刻印を刻印のままにしておくのはまだ早い。その自信とプライドをフィジカルに体現できるその日を、僕は待ちたい。
それまでに「Press On」を歌えるようにしておかなきゃ。お気に入りのプレーンな味のポップコーンを用意して、僕はその日が来るのを待っている。
2006年10月 ロサンゼルスにて
構成・文 ウエヤマシュウジ
Thanks to Neil Oda
|
|