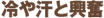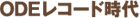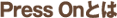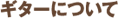|
| ● Talk To T. ● | |

David Tとお話をするスペシャルニューコーナー「Talk To T.」が始まりました。と言ってもDavid Tと話をする機会など滅多にあるわけではありません。2回目が実現するかどうかはまったくわかりませんが、とりあえず第一回目は、2003年8月に実現したDavid Tとの対面のときのことを振り返ってみたいと思います。短い時間でしたが、David Tは実に丁寧に誠実にいろんな話をしてくれました。そこでのお話を彼の発言を交えながら紹介していきます。ご意見・ご感想などございましたら、 管理人ウエヤマ までぜひぜひお送りください! それではどうぞ。 |

|
|
|
●
Top ● About ● 『For All Time』 ● 『Wear My Love』 ● 『Thoughts』 ● Solo album 60's & 70's ● Solo album 80's & 90's ● Unit album ● Band of Pleasure ● David T. Works 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 NEW! ● Discography NEW! ● Talk To T. ● Something for T. #01 タイロン橋本さん #02 清水興さん #03 宮田信さん #04 中村正人さん #05 石井マサユキさん #06 椿正雄さん #07 二村敦志さん #08 鳴海寛さん #09 山岸潤史さん #10 山下憂さん #11 切学さん #12 ニール・オダさん #13 風間健典さん #14 中村正人さん #15 伊藤八十八さん #16 続木徹さん ● Link |