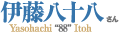|
【後編】

── 伊藤さんのこれまでの経歴でいうと、やはり「ジャズのプロデューサー」というイメージが強いんですが、プロデュースするという立場は、音楽のジャンルによって意識が違うものなんでしょうか?
伊藤:特に違いはありません。でも、どんなジャンルでも自分が感動しないと作れないんですね。自分が感動したもの、感動したエネルギーを作品づくりに向ける。感動の度合いが大きければ大きいほど、クリエイトする意欲がわきますよね。そして長続きもする。だから、一人のアーティストに一枚作って終わるんではなくて、条件が許せば何枚か作りたいと思うんです。ただ、ライヴハウスに行ったりデモテープを聴いたり、特に新人のアーティストなんかだと売り込みもたくさんあるから、あまり数多くは対処できないんですね。だから限られた中でやるしかない。その中で、自分がホントに感動しないと動き出せないというのはあります。
── 感動が根源であると。
伊藤:感動をカタチにする。そして、CDプレーヤーさえあれば、世界中どこでもその音楽を楽しめるように世に送り出す。時間と空間を超越したところで、感動をみなさんに聴いていただくというのが、パッケージビジネスのいいところだと思うんです。
── なるほど。
伊藤:レコーディング終わったらあとはお任せってタイプのプロデューサーやディレクターもいるんですけど、僕の場合は、ジャケットづくりも原稿の校正も自分でやるし、解説も自分で書いたりもします。プロダクトとして、モノづくりとしてきっちりと仕上げる。そこが自分の仕事だと思ってるんですね。そして、いかにスタジオの感動を忠実に盤に込められるか。それが僕の仕事だと思うし、そこまでの責任は持ちたいなと思うんです。
── 伊藤さんが主宰するEighty-Eight'sレーベルは、アナログ盤をリリースしたり、こだわりを感じます。
|

|
|
Hank Jones
『Last Recording』('10)
Eighty-Eightsレーベル
|
|

|
|
Hank Jones
『Jam At Basie』('10)
Eighty-Eightsレーベル
|
伊藤:今年はハンク・ジョーンズさんのラスト・レコーディングと、一関のベイシーっていうジャズクラブでライヴを録音したものと合わせて2枚アナログ盤でリリースしました。確かにアナログ盤聴く人って少なくなりました。でもそういうのを求めている人ってのも確実にいるんですよ。『For All Time』でマスタリングを担当したバーニー・グランドマンさんも言ってましたけど、アナログ盤が少しずつ復活してきてるって。
── そうなんですか。
伊藤:DJとかオーディオマニアの需要じゃないんですよ。一般のリスナー。CDやデジタルで育った人たちが、初めてアナログ盤に接したときに、すごく感動するらしいんです。
── いまや、LPを知らない世代も多いですからね。
伊藤:デジタルとアナログって、理論的には昔からあったんです。レコード盤という形では最初にアナログ盤が先行したというだけでね。デジタルに接して来た人がアナログのあったかい音に接したときに感動するというのは想像できるんです。決してマジョリティではないけれど、何人かの人たちはアナログの音を好きになるだろうな、とは思います。
── デジタルとアナログの違いは昔からいろいろと議論があるところですよね。
伊藤:デジタルって間引いた音ですから。簡略化された音なんです。それをスーパーオーディオCDとか、ビット数をあげたりとかして、間引く単位をもっと細かくしたりとか、結局はアナログに近づけている作業をやってるわけです。究極はやはりアナログなのかもしれないって考えると、レコーディングの機材一つとっても、いろんなことにこだわっていかないと、ホントはスタジオで作った音に近づけないんです。
── うーん、深いですね。でもEighty-Eight'sレーベルの作品は、音についてのこだわりがすごく感じられます。
伊藤:こだわってるんだけど、100%全部うまくいくわけじゃない。これがプロダクトの難しいところで。もっと言うと、CDといえど、同じものは一枚たりともできないですから。
── というと?
伊藤:スタジオで作った音が実際にCDの盤になると音が変わるんですね。さらに言うと、同じ材料、同じ時間、同じ行程で複製しているようでいて、実は全て条件が違ったりするから、プレスされたCDの盤一枚一枚も音が違うんですよ。そのクオリティコントロールは、全世界的に求められているところでもあるんですね。で、みんなそれをなかなか実現できないという悩みがある。作ってる側はそのことを十分にわかってるんです。特にプレス工場の人たちとかね。
── なるほど。
伊藤:プレスにかける時間でも違ってくるし、電圧によっても音は変わる。タコ足配線になってるとダメだし、とかね。日本だとプレス機ってのは連操式で、隣のプレス機の影響で電圧が少しづつ変わって音に影響してくる。ところが、例えば、中国の上海に一つしかないプレス機でやれば、他から影響を受けにくいからいい音で仕上がったりする、だとかね。
── 電源周りは音に影響が大きいと。
伊藤:電源周りだけではなくて振動も重要です。アメリカのプレスがいいのは、工場の地面の土台がしっかりしてることが多いからだったりするわけです。日本の道路ってアスファルトの厚みって30cmくらいだそうですけど、アメリカの道路って50cmから1mくらいあるんですよ。建物の構造一つとっても全く違う。アメリカ人って、ある面アバウトというか、モノの考え方が大きいじゃないですか。だから元々がそういう作りになってる。もちろん彼らがそういうことを考えて工場作ってるわけではないんだけど、そういう文化とか思考が結果的に良い方向に働いてるというか。昔、鉄骨で作られたプレス工場が静岡にあって、振動が影響しないように、近くの川の砂袋をつめて補強、みたいなことをやったことありますよ(笑)。
── へぇー!
伊藤:ソニーミュージックのスタジオでも地下に10トンくらい砂をいれてますよ。そういう微妙なところがたくさんあるんですよ。
── なるほど。
伊藤:デジタルというのは「イチとゼロ」だから変わらない。理論ではそうです。でも、それを取り巻く環境はすべてアナログなんですね。だからどうやってもいろんなことが影響して変化してしまう。こういうこというと、すごくマニアックな世界の話になってしまうけど、でも、実はそういうことなんです。
── スタジオで生まれた音をそのまま伝えることができたら、それは究極ですよね。
伊藤:そうなんだけど、スタジオの音というのも、やはりあるハコの中での音だから、作った音なんです。やはり音楽の楽しさ、醍醐味というのはやはりライヴにあると僕は思うんです。生演奏が原点。それを最大限うまく録音できるのはスタジオという環境である、ということです。
── 今回の新作も作り込まれた部分もあると思いますが、極めてライヴな感じも伝わってきたんですが。
伊藤:そうですね。ライヴな感じに近い、あったかい音に仕上がったと思います。L.A.で録音すると、そういう感じになるというのもあります。やわらかい音というのかな。特にアメリカ人はエコーの使い方がうまいですからね。
── エコー。
伊藤:リヴァーヴですね。日本人と感覚がちょっと違うんです。国民性だからしょうがないんだけどね。
── それはリヴァーヴに求めているものが違うということですか?
伊藤:そうです。日本人はステーキを毎日食べられないですよね。アメリカ人は毎日でも食べられる。合理的なんですね。リヴァーヴってのはある種、合理的に豊かさを演出できる手段なんですね。日本人はそれがなかなかできない。日本人はどうしてもワビサビを出してしまう。あったかい音というのはリヴァーヴの使い方が影響するので、だから日本人とは違う感じになるんです。
── なるほど。
伊藤:例えば、歌舞伎なんかでよく使う「拍子木」の音を録音するとするでしょ? あるアメリカのエンジニアが、その拍子木の音にエコーをかけたことがあったんです。で、それは違うんだよ、という話をするわけです。これはエコーかけずにデッドにしてくれと頼んだんですね。そうすると「なぜ? エコーかけたほうが豊かな音になるじゃないか」というんです。いやいや、そうじゃなくって……てな話を徹夜して語ったことがありましたね(笑)。彼らが特別に考えてそうなってるわけでは決してないんですけどね。ちょっと哲学的でもあるんですけど、でも面白いところでもあるんです。

── 伊藤さんの現在の活動についてですが。
伊藤:やっぱり、新しいアーティストを世に送り出してあげるってところに関わりたいというのはありますね。エネルギーがすごく必要なんだけど。イントロデュースというか、世の中に最初に問う仕事というか。最近だと、まだ18歳だけどサックスプレーヤーの寺久保エレナさんとか、もう20歳過ぎましたけどフランスのトーマス・エンコさんとか10代の頃から関わってます。若くて才能ある人を世に送り出してあげたいなと思いますね。そこは僕のライフワークにしたいと思っているところです。
── これまでも、数え切れないほどのアーティストを世に送り出されたと思います。
伊藤:一方で僕は、ラストレコーディング・プロデューサーって言われてて(笑)。僕といっしょに作ると、その後亡くなっちゃうっていうケースが多いんですよ。
── ハンク・ジョーンズさんのラスト・レコーディングもそうでしたね。
伊藤:音楽のジャイアンツたちの最後の作品を作るところに巡り会えるというのは、すごく稀なことだと思うし、感謝を込めて作りたいと思います。そういう意味では、ファーストプロデュース・レコーディングと、ラストプロデュース・レコーディングと、両方に関われているというのはとても光栄なことだと思いますね。
── 今回のデヴィッドの新作は、ラストレコーディングにはならないと思うんですけどね(笑)
伊藤:もちろん。僕の言うラストレコーディングってのは80歳を超えてるような場合ですから。デヴィッドはまだまだ元気いっぱいです。
── 今回の新作はすごくバラエティに富んでて意欲的に感じますし、すごいなあと思うんです。久しぶりに歌もうたってますしね。あれはデヴィッド自身が言い出したことなんですか?
伊藤:そうです。誰も彼をノセたりしてません(笑)。自ら歌ったんです。とてもシャイな方で、照れながら歌ってましたけど、でも、すごくこだわりを持ってやってましたしね。
── その絵がなんとなく想像できます。
伊藤:デヴィッドって、どちらかというとある種の固定されたイメージというのがあって、そのイメージで聴いている人が多いと思うんです。でも、今回の新作にはいろんなチャレンジがあって、彼のいろんなものが出てると思うんですよ。通好みで聴き手がいかにも喜びそうな部分だけを演るのではなくてね。いつものデヴィッドが聴けるのはもちろん、でも、ホントにオープンなマインドで、いろんなものをさらけだしてプレイしたところもあると思うし、そういうところを聴いて楽しんでほしいですね。
(2010年11月 DCT records本社にて)
ギタリストとしてはもちろん、音楽を形作る役割も自在に担える音楽家、デヴィッド・T.ウォーカー。自身のソロ作品では、ソングライティングや選曲、プロデュースワークを同時にこなすことも多く、最新作『For All Time』も同様にそれら役割を担っている。ただ今回、エグゼクティヴ・プロデューサーであるDREAMS COME TRUEの二人には、ある思いがあった。デヴィッド自身の思いをそのまま活かしながらも、彼の負荷をできるだけ減らし、ギタリストとして音楽に専念できる環境が作れないか。共同プロデューサーをたてるという発想は、そんな意向から生まれた。
かくしてその照準は、日本ジャズ界の名匠に向けられた。特徴的な名前からついた愛称「Mr.88」が形作る音楽は、ミュージシャンだけでは見えにくい、音楽の持つもう一つのポテンシャルを引き出す。そこにあるのは、自らの感動をカタチにするための、想像を超える数々のこだわりだ。共同作業という過程の善し悪しを熟知し、得られる喜びを知り尽くしたセンスと経験は、まろやかな肌触りで主役であるもう一人の匠とも共鳴した。「いつものプロデュースとは違うシチュエーションだった」という回想に、アルバムに新たな試みを注いだデヴィッド・T同様、チャレンジの過程が見て取れる。それは共に、同じ頂きを目指すという意欲の源泉にもなったはずだ。
穏やかで柔らかな語り口や物腰は、シャイで物静かなデヴィッド・Tにもどこか通じる佇まい。永きに渡るキャリアを築き、異なる道を歩んできた二人がクロスした瞬間、それぞれの音楽ヒストリーに新たな息吹が宿った。立場や役割、モノの見方も思考も異なるかもしれない熟達した二人のこだわりとチャレンジの視線の先には、きっと同じ風景が重なり合っている。そのことに気がついたとき、もっともっと、この新作が味わい深く聴こえてくる。繰り返し何度も聴いてみる。彼ら表現者のこだわりと想いに、今度は僕らがそう応える番だ。
聞き手・文 ウエヤマシュウジ
Thanks To Akiko Umegaki
伊藤八十八(いとう・やそはち)
1946年岐阜県生まれ。早稲田大学在学中、ニューオルリンズ・ジャズ・クラブに在籍しJAZZに傾倒。大学卒業後、入社した日本フォノグラム(現ユニバーサル・ミュージック)で洋楽ポピュラー編成部に8年間所属、ポール・モーリア、スコット・ウォーカーなどのポピュラーアーティストを担当する。ジャズレーベル「イースト・ウィンド」を設立し、渡辺貞夫や日野晧正らのプロデュースを手掛けるほか、ダイレクト・カッティングなど、オーディオ・ファイルな作品を多数世に送り出す。1978年にCBS/SONY(現ソニー・ミュージック)に移籍。洋楽企画制作部に所属し、マイルス・デイビス、ハービー・ハンコック、ウェザー・リポートといった洋楽系ジャズを担当しつつ、ザ・スクエアやマリーン、笠井紀美子などの国内ジャズ・フュージョン系アーティストのプロデュースを手掛ける。その後、邦楽制作部門へ移り、久保田利伸、大滝詠一、松田聖子を始め多くのJ-POPアーティストを担当。95年に洋楽部門に復帰し、レガシー&ジャズとアジアマーケティング部を担当。ケイコ・リー、TOKU等を育成する傍ら、Puffyやラルク・アンシエルといった国内アーティストのアジア戦略を計画推進する。99年より録音グループ本部長を兼務し、次世代のSACD(スーパーオーディオCD)の開発や新スタジオ設計・管理に携わる。2001年に、自己の名前に由来したジャズ・レーベル「エイティ・エイツ」を立ち上げ注目を集める。2006年にソニー・ミュージック・グループを定年退職し、株式会社88を設立。現在までのプロデュース作品は国内外を合わせ約450点。多くの作品が米国、欧州、アジアの海外でも発売され、いずれも高い評価を獲得している。
|
|
|