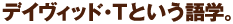|
【後編】

── そもそも、デイヴィッド・Tのギターにハマったのは、どんなきっかけがあったんですか?
風間:私は1950年生まれで、いわゆるほぼ「団塊の世代」なんですね。その世代でいうと、ポップスに目覚めるのがビートルズやベンチャーズなわけです。その頃のヒットチャートって面白くってね。ビートルズとベンチャーズがトップを争うような状況がありつつ、一方でイタリアのサンレモ音楽祭の曲なんかがチャートインしたりとかで、日本独自のヒットチャートが形成されていたんですね。ビルボードやキャッシュボックスのようなアメリカのヒットチャートとは全然違うっていう。日本では我々が中学生の頃にエレキブームになるんですけど、友人のお兄さんがエレキギター買ったっていうんで、じゃみんなで見に行こうみたいな、そんな世界です。昔、『青春デンデケデケデケ』っていう映画があったんですが、まさにあの時代でしたね。
── なるほど。
風間:まだカラオケもない時代だったんで、みんな歌を歌うってことに慣れてなくってシャイだったんですよ。だから、音楽的に何かを表現するってときに、歌うっていうよりギターを弾くっていう発想がうまれて、ビートルズよりもみんなベンチャーズにのめり込むっていうことになるわけです。で、私もそういうのがカッコいいなって思うようになって、高校生のときにギターを弾くようになるんですね。その頃はピーター・ポール&マリーとかブラザーズ・フォーとか、向こうのフォークが日本に入ってきた頃だったんです。教則本を買ってきて、学校から帰ってきたらすぐにギターを触るって毎日で。
── ルーツはフォークだったと。
風間:ベンチャーズ演ってるヤツはベンチャーズだけ、フォーク演ってるヤツはフォークだけみたいに、派が分かれていたんですね。でも、私は両方とも面白そうだったんで、二つの派に顔を出してました。一人クロスオーバー状態で(笑)。でも、エレキギターは高いしアンプも必要だから、最初はアコースティックギターを弾いてました。次第に、仲間うちではちょっとは弾けるっていう存在になって、先輩から文化祭にでるぞって誘われるようになって。ピーター・ポール&マリーのようなスタイルで初めて人前で演奏したんです。その後は同学年の友達とバンドを作ってしばらく演奏することになるんです。
── 最初はエレキじゃなかったんですね。
風間:そうなんです。アルペジオやら3フィンガーピッキングやら。だから、当時の仲間から見たら、未だに私はアコースティックギター弾きっていうイメージが強いかもしれません。
── それがエレキに代わるのはどんなきっかけで?
風間:あるフォークのコンテストがあって出場したときに、すごくPAが悪いことがあって。もともとアコースティックギターって音を拾うのが大変なんですよね。だからステージやるときにもなかなか苦労が多くてね。で、やっぱりアコースティックだと大変だからエレキギターに換えようかってことになるんです。その頃、エレアコの初めとも言えるオヴェイションが日本に入り始めた頃で、一緒にやっていた私の師匠が買ったんです。私はというと、それは高くて買えないのでグレコのレスポールモデルっていうエレキを買うんです。これがスタートですかね。最初はアンプのセッティング方法や歪ませ方がよくわからなくて。当時はクラプトンやらジェフ・ベックやら、ロックは歪ませる、エレキは歪ませる、てのが当たり前だったので、私もそういう感じのものを聴いて挑戦してはみたんです。でも、しばらくすると、そういうロック的な音楽にどうも馴染めない自分がいることに気づいて。
── 馴染めない?
風間:決定的だったのが、あるライヴのときに、物凄いミスをやってしまったんですね。それで、もう自分はこういう音は出せない、ギター弾くのはもう駄目だって思ったんです。
── なるほど。
風間:ウェス・モンゴメリーのようなジャズを聴いたりもしたんですけど、のめり込むって程じゃなくって。こういう音楽もあるんだなって頭に記憶する程度だったんです。元々、フォークやブルースのような、ある意味シンプルな音楽が好きな一方で、映画音楽のようなゴージャスな音楽ってのも好きだったんです。そんなとき、音楽雑誌を見てるとマーヴィン・ゲイってのが目に留まって、レコード評にもよさそうなことが書いてある。で、ライヴ盤を聴いてみるわけです。
── 74年の『Live』ですね。
風間:そうです。あのライヴ盤の「What's Going On」で、歓声があがる直前に入ってくるギターの音を聴いて「うわっ!」ってなって。
── 衝撃的な出会いだったと。
|

|
|
デイヴィッド・Tに“ハマる”きっかけになったマーヴィン・ゲイ『Live』とラヴ・アンリミテッド・オーケストラ『Rhapsody In White』の2枚を手に取る風間さん。
|
風間:でも、そのときはまだそれがデイヴィッド・Tが弾いてるってことも意識しなくって。ただ、あの音、あの全体のアンサンブルにヤラれたという感じで。一方で、同じ頃にテレビのCMでキャセイ・パシフィック航空のCMを聴くんです。
── バリー・ホワイトの「愛のテーマ」ですね。
風間:そうです。で、あの曲はストリングスではなくって、ギターが主旋律だとずっと思ってたんですけどね(笑)。オンエアが終わってしまった後になってすごくあの曲が気になって、いろいろと調べてやっと、そのCMがバリー・ホワイトのラヴ・アンリミテッド・オーケストラの音楽ってことがわかってレコードを入手するんです。ジャケットの裏を見ると、さっきのマーヴィン・ゲイのライヴ盤にもクレジットされてたデイヴィッド・Tの名前を見つけて。音の感じも似てるんで、はああ、このギターはこのデイヴィッド・T・ウォーカーって人が弾いてるんだなって確信するんです。これが彼のギタープレイとの最初の出会いですね。
── ある意味、その2枚はデイヴィッド・Tの代表的なギター作品でもありますもんね。
風間:自分の中では凄い出会いだったんです。というのも、こんな音の表現がアリなんだったら、ギターを弾いてみようかな、と思えたんですね。自分の中にはいわゆるロック的な音ってのは無いなって解ったんです。デイヴィッド・Tがよく「非暴力」の話をしますよね。それにも通じると思うんですけど、私の中にはロックの荒々しさを表現する感覚ってのが無いんだなって。デイヴィッド・Tのギターの音に同じ感覚が見えたんですね。それが最初の彼の音楽との接点だったんじゃないかなって思います。
── なるほど。
風間:デイヴィッド・Tのギターって、躍動感はあるけれども、決して暴力的な音ではない。しかも、きちんとツボを心得てる。全体の構成を考えながら弾いてるっていう。全体が見えてるっていうのかな。そこが凄いなと。そこからはもう、クレジット買いですよ。
── 彼の名前を見つけては買うっていう、そのパターンが始まっちゃうわけですね。
風間:当時、輸入盤屋は少なかったし、雑誌とかラジオでもソウルに関してはそんなに情報は得られなくて。そんな状況でしたけど、それでもなんとかいろんなアルバムを見つけてきて聴くわけです。そうすると、友達にも聴かせたくなるじゃないですか。うちに遊びにくる高校生たちにも聴かせるわけですよ。こういうの演ろうよって。ある意味、その被害者の一人が中村正人君だったわけです(笑)。もちろん彼以外にもいろんな人がいましたけど、一番興味を持って聴いてくれてたのが彼だったんですよね。彼にベースを弾かせて、自分はギターを弾きたかったんじゃないかな?(笑)
── 近くに同士がいたと。
風間:その頃はデイヴィッド・Tなんて知ってる人は周りにはいなかったし、ここまでのめり込んで聴いている人間なんていないだろうと思ってました。でも、その後、82年にクルセイダーズの公演の楽屋でニール・オダさんと会ったんですけど、ニールさんのような人がいたって知ったときは驚きました。自分のことは棚に上げて「凄い人がいるんだなぁ」って(笑)。
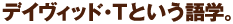
── いろんな人に聞いてるんですけど、デイヴィッド・Tのギターの魅力ってなんなんでしょうね?
風間:もちろんデイヴィッド・Tのギターが好きなんですけど、それだけじゃなくて、L.A.ソウルのあのギターアンサンブルっていうスタイルが好きなんですよ。いわゆるロックなんかのギタートリオのような形ではなくて、ギターがリズム楽器として機能するようなアンサンブルっていうのかな。そういうスタイルがずっと好きなんですね。バリー・ホワイトのラヴ・アンリミテッド・オーケストラでも、ギターが何人もいるでしょ? そういうスタイルです。だからデイヴィッド・Tだけでなくて、ワーワー・ワトソンやレイ・パーカーもコピーしてみましたね。でも、クラプトンやジェフ・ベックの奏法解説は雑誌で紹介されてましたけど、そのあたりのは全く情報がなかったですからね。
── 確かにソウルギターってなかなか陽の目が当たらないというか。
風間:ブルース、ロック、ジャズのギター教則本はあるけど、唯一、ソウルギターってのはないっていう。だからワーワーなんてどうやって弾いてるんだろうって解明するのに随分と苦労しました。でも、ふと間違って弾いた瞬間にたまたまあの音が弾けちゃったりしてね。あ、なるほどこういう風に弾けばいいんだって、変なことからわかったりしたこともありましたね。
── でも、たくさんいるソウルギタリストの中で、やっぱりデイヴィッド・Tってのは風間さんの中で抜きん出ていた存在だったんですよね。
風間:そうですね。ワーワーとレイ・パーカーだけがでてくるギターアンサンブルだと、なんとなく物足りないんですよ。他のソウルギターは「これは他の人でも代われるかな」っていう部分が多いように思えるんですが、私の中では、デイヴィッド・Tの音があって初めてやっとアンサンブルが一つ上の次元で完成するみたいな感じです。さらにその上をいくギターっていうんでしょうか。
── なるほど。わかる気がします。
風間:ここでこうなると、次にこう来るっていう、デイヴィッド・Tのフレーズのパターンってありますよね。次はこうくるだろうって予測ができる音というか。そしてやっぱりそうなったとき、あ、これは彼が弾いてるんだなって確信できるっていう。その音が来るところで来てほしいんですよね。それが無いと寂しいんです。水戸黄門の印籠じゃないけど、ここでこう来てくれるとうれしいっていうパターンを見事にやってくれるのがデイヴィッド・Tで。
── それだけ聴き込んでるからということだけじゃなくって、ギターそのものが特徴的だっていうことですよね。
風間:ストリングスや他の楽器がたくさんいて、彼のギターはしばらくほとんど聴こえてこないんだけど、でも最後にちょろっと出てくるところで存在感を見せ付けるっていうか。あ、やっぱりいたんだっていう。その音が聴けてうれしいっていう感覚。その立ち位置っていうのか、目立ち方っていうのか、そういうところが物凄く好きなんですね。
── 出過ぎず退き過ぎずの感覚。でも妙に引っ掛かってくる音の感覚っていう。
風間:デイヴィッド・Tのギターで、スライドアップしながら高音部に駆け上がっていくようなフレーズがありますよね。あの駆け上がっていくスピードって、均一じゃないと思うんですよ。始めはゆっくりと、段々とスピードアップしていってるように感じるんです。そして、小節の頭にピタッと入り込んでくるあの絶妙なタイム感。それがデイヴィッド・Tのギターのスピード感のような気がしますけどね。
── なるほど。
風間:そんな特徴的なフレーズに、私自身がギター弾く上で影響受けるわけです。ある意味では、語学のようなものですよ。
── 語学?
風間:そう「デイヴィッド・T語」のね。彼のフレーズが彼の言葉だとすると、私自身がギター弾くときっていうのは、その言葉を使わせてもらって、自分の会話の中で喋ってるのと同じっていうか。彼だったら、この場でどう言うだろうかっていうことを考えるっていうのと同じっていうか。このコードが出てきたら、こう弾くだろう、とか。そういうことを考えるのも楽しいし、彼のファンの一つの楽しみ方だとも思うんですよね。言葉として考えると、彼はそんなに雄弁じゃない。幾つかの決まりがある中でフレーズを作ってる。でも、そのフレーズを使うところのセンスが抜群に素晴らしいんですよね。
── ああ、なるほどー。
風間:私は、これまで音楽の制作っていう部分では彼と一切関わってないんです。たまたま広告の仕事で彼と関わったりはしましたけど、基本的には全くのファンの立場でデイヴィッド・Tと接する事ができてて、それでも、彼は私のことをずっと覚えていてくれてる。フレンドだって言ってくれる。そのことをとても光栄に思うんです。ファン冥利に尽きるってところです。
── 彼らしい接し方ですね。
風間:彼とはいろんな話をしましたが、彼に会って感じたのは「あ、やっぱり音の通りの人なんだな」ってことだったんです。彼のギターを好きになって、こんな音を出すのはどんな人なんだろうって考えてたんですけど、会ってみて、やっぱり自分が思ってた通りの人だったなって。私自身が「こう在りたいな」っていう在り方と重なっているように感じたので、良かったなって思ったんです。それでさらに彼のファンになったんですよね。ガチガチの生真面目な人でもない。周りがノセればちょっとしたワルノリもできるっていうところも含めてね。クルセイダーズのコンサートのときに、途中で盛り上がって、バックの3人でラインダンスをやってたこともありましたね(笑)。
── 想像つきますね(笑)。
風間:といってもシャイな感じでやるんですよ。そこがまた彼の人柄なんでしょうけどね。目立ち過ぎず退き過ぎずっていう、あのスタンス。抑制なんだけど、でも、それでも自然と溢れ出てくるものがあるっていう。そしてあのジェントルな感じ。きっとそこが、みんなを惹き付ける彼の魅力なんだろうなって思うんですよ。
(2007年6月 千葉県市川市にて)
数ある音楽家の中で、デイヴィッド・T・ウォーカーという存在ほどコレクター心理を掻き立て増幅させる対象はないのかもしれない。「もっともっと彼の音を聴きたい」というシンプルな欲求が、いつしか「コンプリート」という魅惑に姿を変える。その姿は、膨大な量と質の仕事をこなした巨人への溢れる愛情の裏返し。その軌跡に圧倒され続けるファンの奇異な敬意のあらわれだ。
世界有数のデイヴィッド・Tコレクターにして研究家。筋金入りの探求ぶりは他の追随を許さない驚愕の偉業だ。同じデイヴィッド・Tファンとして、これまで何度もお会いしデイヴィッド・T談義に華を咲かせ、昔のエピソードを楽しく聞かせて頂きもした。穏やかな会話の中から溢れる音楽力。そのテンポが実に居心地いいのだ。
来日したデイヴィッド・Tに「愛用のギターを持っておいでよ。一緒にプレイしようよ」と何度も言われ続けているという。それが未だに実現されてないことを「なんだか恐れ多いんですよね」と控え目に答える風間さん。その表情はどこかデイヴィッド・Tの穏やかな風貌と重なり合う。満面の笑みで言葉を交わすそんな姿を見る度、奇妙で不思議な縁で結ばれた彼ら二人の関係性に興味が沸いた。それは彼が稀有なコレクターだからという理由だけではない。
出過ぎず退き過ぎず。敬愛するギタリストの姿に自らの姿が重なったことの幸福が、ファンという立場で30年以上も一人のアーティストを追いかける源泉となった。そこにあるのは、お互いを“フレンド”と呼び合える信頼関係。年月をかけてゆるやかに同期した穏やかな歩調だ。
いつの日か、デイヴィッド・T語という共通言語で会話する彼ら二人の姿を見てみたい。きっとそれは、流暢で優しく、弾んだものに違いないのだ。
(聞き手・文 ウエヤマシュウジ)
風間健典(かざま・たけのり)
1950年8月3日、千葉県市川市国府台生まれ。千葉県立国府台高校卒業後、早稲田大学政治経済学部入学。二留中の大学在学時に、高校の同窓8期違いの後輩、ドリームズ・カム・トゥルーの中村正人氏と同じバンドで活動。大学卒業後、銀行に就職するが、音楽に近い暮らしがしたくなり退社。1年半の浪人生活の後、1980年、新聞広告で募集のあったパール楽器製造に入社。電子楽器担当の販売促進&セールスエンジニア&企画宣伝&アーティストリレーションを兼任し、その縁でデイヴィッド・T・ウォーカーと出会う。その後、楽器関連の広告代理店に勤務し、楽器の広告・カタログ・取扱説明書等を中心に制作・営業の仕事に従事する。病気入院をきっかけに退社&独立し、生活をスローダウン。取引先や前の会社、友人など、周囲の厚意に感謝しつつ、日々を送る。2007年7月発売の中村正人氏のブログ本には“音楽の先生”と紹介されている。
|
|
|