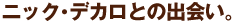|
【後編】
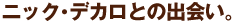
── ニック・デカロとはどんなつながりがあったんですか?
ニール:阿川泰子さんの『Your Songs』ってアルバム作るときに、オレも企画会議から参加させてもらってて。次はスタンダードナンバーでやろうかって話になったときに、ジャズじゃなくてポップスでいこうってことになったの。だったらストリングス入れてやってみたいって話をして、誰にアレンジを頼もうかってことになっていろんなアイデアがあったんだけど、オレはクラウス・オガーマンがいいって言ってたの。で、アル・シュミットに連絡して相談したら、別の仕事があってダメっぽいと。ジーン・ペイジはどうだろうってアイデアもあったけど、でもソウルっぽくなるからどうかなあって悩んでいたときに、ふと、ポップスとA&Mっていうキーワードが繋がっちゃったんですよ。
── それで、ニック・デカロ、と。
ニール:うん。アルから連絡先を聞いてお願いしたらOKってことになってね。そのときのディレクターだった星加さんって人がニック・デカロ大好きな人だったんで、どうせやってもらえるんだったら歌も歌ってもらえないかなって話になって、ニックにバックボーカルもお願いしたのね。それこそ、何十年ぶりに歌います、みたいな世界でさ。で、こうなったらニックのソロアルバムをなんとか作れないかってことになるわけですよ。でもそのときはレコード会社から即座に却下されたんだよね。ニック・デカロ?誰も知らないよそんなヤツって。でもね、せっかく本人が目の前にいるのにあきらめきれなくて。
── そりゃそうですね。
ニール:で、ふと思い出したの。以前、山下達郎さんと話をする機会があって、そのとき達郎さんがニック・デカロの『Italian Graffiti』が大好きだって話をしてたことを思い出したんだよね。そこで考えたのが、当時、カヴァーアルバムが流行ってたということもあったので、ニック・デカロが達郎さんの歌を歌うってアイデアだったの。でも達郎さんは他人に自分の曲を今まで一度も歌わせてないからダメなんじゃないかって、その星加さんと話をしてたんだけど、でもオレはその以前の達郎さんとの会話の中で、相手がニック・デカロだったら絶対OKしてくれるって確信してたの。で、達郎さんの事務所を通して話をしたらOKしてくれてね。
|

|
|
Nick Decaro
『Italian Graffiti』('74)
トミー・リピューマ、アル・シュミットの黄金コンビによる珠玉の一枚。デイヴィッド・Tもきらびやかなプレイで参加している。
|
|

|
|
Nick DeCaro
『Love Storm』('90)
山下達郎さんの楽曲をニック・デカロが歌うというニール・オダ氏プロデュースの一枚。この後、ニック・デカロはデイヴィッド・Tらによるバックバンドを率いての来日公演も行った。
|
── 作戦勝ちですね。それが『Love Storm』ですね。
ニール:そう。ニックはなかなか気難しいところもある人で、レコーディングはいろいろと大変だったけど(笑)。でもいい仕事だった。今でも彼にもらった形見の帽子を持ってますよ。
── 『Italian Graffiti』の次のアルバムを日本で作ったんですからね。喜びもひとしおだと思います。
ニール:『Italian Graffiti』ってアルバムは極上のアルバムでしょ? オレ、トミー・リピューマになりたかったんだよね。
── ああ、なるほど!
ニール:ブルーサムでのトミー・リピューマの先見性はホントに凄いと思ってて。オレにとっては憧れのレーベルだったのよブルーサムは。ニック・デカロやクルセイダーズがいるってだけじゃなくて、ダン・ヒックスとかね。あの時代にルーツ音楽でありながら、どこかお洒落でもあるっていう音楽を作ってたレーベルじゃない?
── 確かに。ベン・シドランなんかもいましたよね。
ニール:とにかくトミー・リピューマって人には影響を受けてね。で、運良くオレはアル・シュミットと仲良くなれて。トミー・リピューマといえば、アル・シュミットでしょ? で、デイヴィッド・Tにニック・デカロとくれば、オレはもうトミー・リピューマになるしかないでしょ?みたいな(笑)。
── トミー・リピューマ本人とはお会いしたことあるんですか。
ニール:うん。そのニック・デカロのレコーディングのときにスタジオに遊びに来てくれたの。緊張してほとんど喋れなかったけど。でもね、そのとき「今回はお前だな」って言われたの、トミーに。
── え? それはどういう意味で。
ニール:前回ってのはつまり『Italian Graffiti』のことで。「前回はオレが作ったけど、今回はお前が作る事になったんだな」っていう。
── それはうれしい一言ですね。
ニール:あのとき、オレのもう一つの夢を叶えた瞬間って感じだったよね。とにかく『Italian Graffiti』ってアルバムが大好きだったから。オレにとってはホントに大きな出来事だった。デイヴィッド・Tといっしょに来日公演まで実現できたし。まさかオレもニック・デカロといっしょのステージに立つとは思わなかったよ。残念なことに、それがニックの最後のステージになってしまったけどね。

── 夢を叶えた後、ニールさんとしては、次に何をしようと考えたんですかね?
ニール:デイヴィッド・Tのソロアルバム3枚作ることができた。いろんなミュージシャンとも知り合えて交友関係も大きく拡がった。ある意味、それでオレの夢は叶っちゃった。だけど、その後、実はいろんなことがあってフェードアウトしちゃったのよね。何か目標を失っちゃったみたいなところもあって。
── フェードアウト?
ニール:文字通り、消えちゃったんですよオレ自身が。仕事の現場からね。当時はバブルの頃で、何かと有頂天になってたんだと思う。自分自身、舞い上がってたし、まだまだ人間的にちゃんとできてないってところもあって、いろんな事にナイーブだった。で、あるとき、自分の中でプッツリと何かがキレちゃって。病気になって、破産したり、離婚したりといろいろあって仕事も信頼も失ったんだよね。で、いきなり周囲に何も言わず業界からも姿を消しちゃったの。
── いきなり、ですか?
ニール:デイヴィッド・Tにも何も言わずに姿を消しちゃったからね。後で聞いたらだいぶ怒ってたみたいだけど。
── それからデイヴィッド・Tとも連絡せず終いで?
ニール:5、6年くらい経ってかな、連絡とったの。最初はもう元には戻れないな、って思ってたから。なにしろ辞めた当初はホームレス同然だし、なにより普通の状態じゃなかったからね。自分の壊れていたところを直す必要もあった。周囲からもいろいろ言われてたみたいだし、天国から地獄って感じで、それはやっぱり辛かった。もちろん自分のせいなんだけどね。元々、オレはルーズでいい加減な性格で、なにしろ努力と忍耐が嫌いなタイプだから、それまでも好き勝手に生きてきたからね。そういう意味ではアクシデントというより必然の経験だったと今は思うけど。
── なるほど。
ニール:ただ、急に黙って消えたから人間関係が完全に崩壊しちゃって、それはやっぱり大変な事だった。その時オレにはもう家族もなかったし、人と会う機会も気力もなかったしね。今で言う引きこもりですよ。じっと音楽だけ聴いてた。で、数年してやっと日本食レストランで皿洗いの仕事をできるくらいになって。プロデューサーから皿洗いって、凄い転落人生みたいだけど、でも実はそれほど悲観的じゃなかった。また一からやり直しって感じではあったけど、でも音楽はずっと身近にあったし、次第に支えてくれる人もでてきて新鮮に再スタートしたって感じではあったの。普通の小さな事に幸せを感じられるようにもなったし。で、以前はアメリカと日本を行ったり来たりしてたけど、アメリカに残るにはグリーンカードを取らなきゃならなくなったんだよね。それには推薦人が必要だった。でもオレの推薦人になってくれる人なんて誰もいない。どうしようかなと思ってたときに、デイヴィッド・Tとアル・シュミットが「そういうことは人生の中でいろいろある。後はどうやって自分を立て直すかだから。ちゃんと戻って来たんだったらオレたちはまたお前を信用できるから」ってことを話してくれて。
── ふむふむ。
ニール:オレたちが面倒みてやるって、彼らが推薦人になってくれて、グリーンカードがとれたの。だから彼ら二人には厚い恩があるんだよ。よく信用してくれたなって思ったけどね。
── そうだったんですか。
ニール:デイヴィッド・Tとかアル・シュミットもそうだけど、彼らのような人たちって、過去にいろんなことがあったりもしてるわけじゃない? 時にはハメ外して良くない事態になったりとかさ。そういうところから「戻ってくる」ってことをいろんな意味で経験してるんだよね。そうやって「戻ってきた」人間にしかわからないことってのがあるのかなって思った。戻ってきたときに世間がどういう風に自分を見るのかとか、どういう扱いをされるかとか、そういうことを含めて、彼らはそんな経験をして今に至ってるんだなって、そのときすごくよくわかったのね。それが彼らの大きさなんだなって。懐の深さというのかな。やっぱり深いんだよ。それは音づくりの深さといっしょなんだよね。真っ正直に美しく生きていくことは大事なことなんだけど、でも、それだけでは出せない「深さ」ってのがあるんだってことをね。彼らと比べると自分の出来事は全く次元の違うことだと思うけど、自分自身もそういった経験をして、あらためて彼らの深さを知った、というか。
── 人間の深さ。
ニール:デイヴィッド・Tは、見た目はホントに丸い穏やかな感じの人だけど、その中の中の中には、すごく尖ったものがあるんだよね。それを決して外に出さないってところが凄いところなんだけど、どうすれば出さずに済むのかずっとわからなかったんだよ。やっぱりさ、やりたくないことをやれって言われたときに、嫌な顔一つしないってことは、いいことのように思われるけど、実際に自分がその立場になったとき、それがいいことだとは思えないわけさ。嫌なことは嫌ってハッキリいったほうがいいじゃん?って思うわけ。でも彼はそうしないんだよ。例えば、世界中が戦争やってるときに「Ahimsa」なんて言ってる場合じゃないでしょ?「On Love」なんて言ってる場合じゃないでしょ?って言いたくなる人もいるかもしれない。でも、彼はそれをどんな時にでも言っちゃえる人なんだよね。表向きとか気分的にではなく確固たる信念と、酸いも甘いも知った上での確信みたいなものもあるんだね。だからその「どんな時でも言っちゃえる」ってところに、底知れぬ深さがあるってこと。ただの「いい人」だったら、そうは言えないんだよね。
── なるほど。
ニール:表に出て尖っていたものの上に、経験によって作られた心とか体を被せていくことで尖りが無くなると、尖ってたものが外に出るってことが無くなるんだよね。その被せてきたもの、の重さっていうのがすごくあるんだなって。
── うーん。深いですね。
ニール:グレイトフル・デッドのジェリー・ガルシアってギタリストがいるでしょ? デイヴィッド・Tと彼はすごく近い人だと思うの。似てるところがあるんだよね。オレはガルシアのギターも味があってすごく好きなのね。フレーズとか音とかスタイルは全く違うんだけど、どこか通じるところがあるっていうか。感情をむき出しにとか、感情そのものをギターで弾くってことじゃなくって、逆に、むき出しのものをむき出しにしないで音にして、その上でなお、むき出し感を聴く人に伝えるっていうか。うまくいえないんだけどね。人としての大きさや深みが音になっているんだけど、実はそれはむき出しのものではないっていう。「底が丸見えの底なし沼」って感じかな?
── 何となく、わかるような気もします。
ニール:クラプトンなんかもそうなんだよね。今のあの人の丸みも似たようなところを感じるの。だからオレ、デイヴィッド・Tとクラプトンを共演させたかったんだよ。
── へえー。
ニール:昔、ジョン・レノンのトリビュートアルバムを作ったことがあって。『Love John Lennon Forever』っていうアルバムなんだけど。あのアルバムにクラプトンが参加するはずだったの。クラプトンもぜひ演りたいって言ってくれてて。
|

|
|
Love John Lennon Forever
『Love John Lennon Forever』
('91)
|
── そうだったんですか。デイヴィッド・Tとクラプトンって共演したことないですよね?
ニール:ない。一度もないんだよ。でもお互いはお互いのこと知ってて。で、レコーディングの日まで決まってたんだけど、直前にクラプトンの息子さんがビルから落っこちて亡くなっちゃったんだよね。それで中止になった。これはどうしようもなかった。残念だったけどね。
── そうですか。
ニール:ジェリー・ガルシアともデイヴィッド・Tを共演させてみたかったんだけどね。あのヒゲ面が二人並んでるっていうね(笑)。残念ながらガルシアは亡くなっちゃったから実現できないんだけど、クラプトンはまだ現役だし、いつかって想いもあるんだよね。だってさ、あの二人が並んでギター持って座ってるだけで絵になるじゃない?
── 確かに(笑)。
ニール:それから、デイヴィッド・Tはノラ・ジョーンズを気にいってた。彼女といっしょに演ってみたいって言っててね。で、こないだレイ・チャールズが死ぬ直前に録音したアルバムでノラ・ジョーンズが参加してるヤツがあったでしょ。あれにデイヴィッド・Tも実は録音に参加してるのよ。でも結局、そのテイクは使われなかったようで。それでノラ・ジョーンズを知ったらしいんだけどね。で、しばらくの間、彼女のことをいろいろ話してたのよ。オレもノラ・ジョーンズいいよなあって思ってたから、彼女とデイヴィッド・Tをいっしょに演らしてみたいな、なんて思って。
―― いいですね。その組み合わせは聴いてみたい。
ニール:もしそういうチャンスがあったら、デイヴィッド・Tのギターとクラプトンのギターで、ノラ・ジョーンズが歌うっていうね、そういう展開っていいなあって思うんだよね。ぜひ聴いてみたい組み合わせだね。

── デイヴィッド・Tの新作レコーディングについてですが。
ニール:随分と長くソロアルバムを作ってないから、新作はある意味、カムバック的アルバムじゃない? だから最初はファンサービスのアルバムにしようって二人で話してたの。だから、みんながどういう音を望んでるかアンケートをとってもらったんですよ。
── たくさんの人にアンケート書いていただきました。
ニール:二人でそれみてホントにうれしかった。デイヴィッドも喜んでててね。みなさんにお礼を言いたいです。ありがとうございました。
── アンケートの結果を見て、デイヴィッドとはどんな話をしたんでしょうか?
ニール:まず感じたのは、やっぱりみんな70年代のデイヴィッド・Tが好きなんだなってこと。当然といえば当然のことなのかもしれないけどね。でも、そういう音を今やるってのは、やっぱり退行してるって感じもあった。同窓会のようなアルバム作ってチャンチャンって感じだったら、何となく納得いかないってところもあったの。で、二人でいろいろ話をして、だったら新しいことやろうよってことになったんだよね。
── 難しいところではありますよね。リスナーとしては70年代のあの音を、ってところも大きいし、でも作る側はそうじゃないって部分もあり。
ニール:そうだよね。でもこういう話になっても、みなさんからのご意見があったからこそって事は伝えたいな。みんなの声はしっかりとデイヴィッドに届いてます。彼がこれからどんなものを作っても、その声は無駄になってはいませんから。これからもよろしくお願いします。
── ありがとうございます。そう言っていただけるとみなさんもきっと喜ぶと思います。で、結果、どんなカタチに話がまとまったんですか?
ニール:実は、デイヴィッドと二人で一致したのが「フルストリングス・アルバム」を作ってみたいねってことだったの。
── フルストリングス・アルバム。
ニール:ウェス・モンゴメリーのストリングスアルバム(=『Fusion ! : Wes Montgomery with Strings』)のような感じのね。デイヴィッド・Tはぜひ演ってみたいって言っててね。オレはオレで、デイヴィッド・Tにストリングス満杯の音の中であのギターを弾いて欲しいっていう想いがあって。メロウっていうよりロマンティック。ひたすらロマンティックな音だけを作ってみたいっていう。バイオリンのセットを少し多めにするとデイヴィッド・Tの音域にぴったりハマるなあって。リズム隊は極力少なくして。こんな感じの曲あんな感じの曲やろうよって、二人の頭の中ではもう音は鳴ってたんだよね。
── なんだか素敵な構想ですね。
ニール:デイヴィッド・Tのブルージーな部分ではなくて、ロマンティックな部分を全面に出したアルバムってのを出してみたかったし、聴いてみたいっていうね。で、歌は一切入れない。
── その辺りはこだわりで。
ニール:デイヴィッド・Tは歌モノのバックで弾いてるところがいいってみんな言うし、オレも実際そう思う。でも、デイヴィッド・Tのソロアルバムで歌を入れて、そのバックで弾くデイヴィッドっていうカタチは、彼にとってはやっぱり歌のバックでしかないんだよ。彼は、歌のバックで自分だけが目立つような弾き方が出来ない人だから。歌を引き立てるためにギターを弾くから。
── なるほど。
ニール:もう年だからさ。ホントに彼が納得できるアルバムを作ってあげたいと思うんですよ。なんて言うとさ、生きてピンピンしてるのに怒られちゃうけど(笑)。契約の問題とかいろいろあって、なかなか思うように進まないのでデイヴィッド・Tにも申し訳ないなとも思ってる。だから、もちろんそこに自分が関われたら最高なんだけど、でもそうでなくってもいいんです。だけど、デイヴィッド・Tの最後の一枚のソロアルバムが、歌モノのバックの演奏ばかりだっていうんだったら、それはナットクいかないっていうか。やっぱり、デイヴィッド・Tのある側面をデフォルメしたようなアルバムを作りたいって思うんだよね。それがブルースなのかジャズなのか、もしくはロマンティックな側面なのかは、わからないけど。
── ふむふむ。
ニール:一時期はね、ジャズのスタンダードナンバーをトリオで演ってみたいっていうことは話もしてたのね。でもそれだとなんとなく音が見えちゃうから、カルテットだったら面白いかも、とかさ。で、そうなるとピアノは絶対フェンダーローズで、CTIっぽい4ビートでね、とか。それだと、よくあるタイプのジャズギタートリオじゃないし、ちょっと違った雰囲気でいいんじゃない?とかさ。チェットベイカーのCTIのアルバムを二人で聴いてね。このトランペットの代わりにデイヴィッドのギターが鳴ってるってどう?みたいな。デイヴィッドも「いいね」って。
── うーん!
ニール:本人はブルースがとても好きだからね。でもオレはブルースじゃないものを演らせてみたいっていうところもあって。ブルースやるんだったら歌をうたってみたら?って提案したら却下されました。「オレは歌がうますぎるから歌わないんだ」って(笑)。

── ニールさんの現在の音楽活動について教えてください。
ニール:今、いろんな音楽活動をしてるんだよ。ソロ・アーティストとしてニューヨークのレコード会社と契約してアルバムを作ったり、映画やテレビ、Web用の音楽を作る仕事なんかもやってる。ちょっと前だけど、マイケル・ジャクソンの「Beat It」って曲のプロモビデオを撮ったボブ・ジラルディって監督が撮った『ディナー・ラッシュ』って映画に曲を提供したりとか。あと、光瀬直毅っていうとても才能のある絵描きでアニメーターの友達がいるんだけど、彼はフラッシュのムービーも作っていて、そのムービーに音楽をつけたりもしてます。それはヨーロッパで賞ももらったし、アルバムとしてリリースもしたんですよ。2000年に出したアルバムはこっちのKCRWをはじめとするラジオ局でもたくさんオン・エアーされて。今でもよくラジオから流れてくるし、ケーブルやサテライトTV、それにファッション・ショーで使われたり、「長く聞かれる」作品になったと思うので、たいして売れなかったけど自分では成功したと思ってる。
── ふむふむ。
ニール:メジャーなコンテストで入賞したり、権威あるレビューで4ツ星とって絶賛されたりもしたし。失った自信を取り戻したというか、ミュージシャンとして初めて評価されたという意味でもいい作品を作れたと思った。タイトルが『Eclipsing The Past』ってのも意味深でしょ? このアルバムはヨーロッパやアジア、カナダとかでも発売されたんですよ。
|

|
|
Ultralights
『Eclipsing The Past』('00)
ニールさんがSunday Mitsuru名義で参加しているUltralightsの1stアルバム。
|
|

|
|
映画『ディナー・ラッシュ』(写真はDVDのジャケット)
ボブ・ジラルディ監督によるこの映画にニールさんは音楽を提供。
|
|

|
|
Sunday Mitsuru / Ultralights
『Ark Of The Universe』
2007年春リリース予定の2ndソロアルバム。
|
── ワールドワイドにやられてるんですね。
ニール:開かれた場所にいるからね。やってて面白いよ、いろんな国にファンがいてくれて。そう、自分のアルバムを作ったときに、デイヴィッドにギターを弾いてもらおうかとも思ったのね。結局、弾いてはもらわなかったんだけど。後でデイヴィッドにも「なんで呼んでくれなかったんだ。言ってくれりゃ弾いたのに」って言われたりもしたんだけどね。でも、オレの中でデイヴィッド・Tという存在は凄く大きいんで、彼にオレの音楽を弾いてもらうっていう発想が実は無いんだよね。オレが彼の音楽にヘルプする、例えばプロデュースしたり、ディールをとったり、プロモーションしたりっていう、そういうカタチで彼にヘルプするってことはあるけど、彼がオレの音楽にヘルプするってのは、ちょっと考え辛いものがあるんだよね。
── それはなぜなんですか?
ニール:普通ね、ミュージシャンだったら自分の音楽にデイヴィッド・Tにギターを弾いてもらいたいって思うじゃない? あと、オレが自分の音楽を作るときに、オレが今まで関わったいろんなミュージシャンを集めたら結構豪華な顔ぶれになったりもする。でも、それはもはやオレのアルバムじゃないっていうことなんだよね。ある意味それってクインシー・ジョーンズ化するってことだし。今までオレはプロデューサーとしてやってきたけど、ミュージシャンとして自分の音楽を表に出したことはなかったんだよね。だから、オレが音楽を作る人だってことを誰も知らなかった。もちろんデイヴィッドはいっしょにやってきたからオレがシンセのプログラミングをやったりとかアレンジをやる人間だって知ってるんだけど、まさかオレが自分で曲を書いたりする人間だって思ってなかったみたいなんだよね。だから、オレが自分のソロアルバムを最初に作るときは、すべて自分一人で作って、こういうこともできますよってのを示したかったのね。で、ヨーロッパとかカナダとか香港とか、ワールドワイドにそれなりに反響があったので、2枚目を作ろうと。ヨーロッパのケルトミュージックというか、中世紀の音楽に興味があって、それをエレクトロニカで作ってみたくって、そういう音楽をやっぱり一人で作ったのね。マンドリンとかバイオリンとか、アコースティックな音もいっぱい使ってやってみたんだよ。ジェネシスとかピンク・フロイドみたいなプログレっぽい事とかも取り入れて。だからちょっとアヴァンギャルドな雰囲気になっちゃってデイヴィッド・Tの音楽とは違うし、今回も弾いてもらえないなぁ〜(泣)ってね。だけど、いつもサンクス・クレジットには彼の名前が入ってるの。
── 弾いてもらってはいないけど?
ニール:そう。普段の生活から何から、ありとあらゆる意味で、今こうやってオレが音楽を作ってアメリカで生活できているのも彼のおかげだしね。精神的にも助けてもらっているところも大きいし。
── なるほど。
ニール:あと、そういう偉大な人たちと仕事ができたおかげで、オレの耳が巨大になったというか。ものすごく大きなものを得たんだよね。しかも真横で見ながらね。彼らがどういう風に音を飲み込んで消化していくのかってことを俯瞰して見れたわけ。特にデイヴィッド・Tには音楽に対しての立ち位置を教えてもらった。ギターを演奏できてうれしいっていう欲望と、売れたいっていう欲望と、いいものを作りたいっていう欲望、そういうもののぶつかり合いみたいなものをすぐ傍で見れたんだよね。そういう経験というのは、オレといっしょに演奏してもらうということ以上に、オレにはプラスになってる。そういうことを含めた「サンクス」なの。そういういろんなことをオレなりに吸収することができて、オレの音楽が出来上がっているというか。だから、デイヴィッドがギターを弾いてなくっても、いっしょに演ってるような感じなの。自分の音楽にデイヴィッドのギターが鳴ってたらいいな、っていう感覚よりもむしろ、デイヴィッドだったらこういうときどう考えるだろうか、とか。オレはミュージシャンとしては一般的にあまり知られてはないんだけど、いちミュージシャンとして、他のミュージシャンとはその辺りでちょっと違う感覚があるのかなって思うんだよね。
── 確かにそうかもしれませんね。あまりにもデイヴィッド・Tに近い存在なだけに。
|


|
|
ニールさんがドラマー&マンドリンで参加しているカントリーバンド
The Running Kind。写真左からNeil Fukasawaことニール氏(ds, mandolin, vo)、George Alexander (g, vo)、Leslie Ann Bosson (vo)、Matt Bosson (vo, g)、Frank San Filippo (b)
|
ニール:最初に言ったけど、オレの音楽のスタートってカントリーなのよ。で、今、オレは自分の音楽を作るってこと以外に、カリフォルニアのクラブサーキットで活動している「Running Kind」っていうカントリーバンドでドラムとマンドリンを演奏してるんですよ。オーディション受けて受かったんだけど。ナッシュビルじゃなくても、カントリー・サーキットってあるんだよね。結構ファンも多いし。やってみてまだ知らないミュージックシーンがあるもんなんだなぁーって驚いたね。
── なるほどー。
ニール:で、こないだデイヴィッド・Tにその話をしたら、すごく喜んでくれたのね。「テンガロンハットかぶって見に行く」って言ってくれて(笑)。オレがデイヴィッドと離れている状態で、オレが音楽に何もタッチしなくなったら彼は「寂しい」っていうんだよね。でも、自分が自分の音楽を楽しんで演っている、それがカントリーであろうが何でもいいんだけど、そういうエンジョイしているっていう様子を聞けると「うれしい」って、そう言ってくれる。オレとデイヴィッド・Tの二人はそういう関係なんだよね。音楽というものを挟んで距離を保っていく。プライベートにはほとんどタッチしない。音楽を自分の人生の中にどうやって取り入れていくか、自分の中で音楽というものをどうやって存在させていくか、ってことをオレはデイヴィッド・Tから学んだのね。それをどうやって実践していくかを考えて、その結果「お前はこんなふうに音楽と暮らして生きているんだね」っていうところを認めてくれているっていう。デイヴィッドがオレを見る眼差しってのは、オレがどれだけ音楽を楽しんでいるかってことなんだよね。それさえクリアしてれば、安心してもらえるっていうか。
── ……(泣)。
ニール:オレのソロアルバムでも「ぜひ弾かせろ」って言ってくれるし、カントリーのバンドでも弾かせろって言われるんだよね。確かに、カントリースウィングみたいなのを一度彼に弾かせてみたいっていう気持ちもあるんだけど。ああいう音楽にデイヴィッドのギターは実はハマるんじゃないかって密かに思ってるんだけどね。でもさすがにテンガロンハットは被らないだろうなあ(笑)。
── (笑)。見てみたいですねデイヴィッドのテンガロンハット姿。でもニールさんにはデイヴィッド・Tもいろいろ言うんですね(笑)。
ニール:オレには喋りやすいってところはあるかもしれないね。それと、オレが必要以上に音楽好きだってことなんだろうなって思う。いろんな音楽を聴くのが好きだしね。
── それはこの部屋の大量のCDをみればわかりますよ(笑)。
ニール:この家には、こないだ引っ越してきたんだけど、デイヴィッドが最初に遊びに来たときにオレが「もうちょっと大きな家に住みたかったんだけどねー」って言ったら、彼は「何言ってんだ。これだけのCDがある限り、お前は幸せなんだからいいじゃん」って言うんだよね。つまり、音楽に囲まれている以上は幸せでいられるっていうこと、それがオレであるってことをデイヴィッドがわかってくれている。ビジネスの部分はビジネスの部分であるんだけど、それとは別に、どれだけ深く音楽に入り込めているかを、彼にはいつも見極められているようなところがあるんだよね。それが、彼のオレに対する信頼感なんじゃないかなって思う。彼が突拍子も無い事をオレに言ったとしても、それが音楽の話だったらきっとわかってもらえるっていう思いがデイヴィッドにはあるっていうか。オレの音楽性がどうのこうのではなく「音楽のライフ」っていうのかな。そこが唯一の絆っていうか。オレの音楽に対する姿勢を好きでいてくれている、っていうかね。
── 絆。
ニール:初めて会ったときはめちゃめちゃ距離感があった。遠い遠い存在。でも、ホテルに呼ばれて行って話をしたときに、なんか瞬間的に3光年くらい距離が縮まった気がしたのね。で、初めてロスにやってきて会ったときに、また3光年くらい縮まって。そうやって段々と距離が縮まっていく感じにはなるの。でもね、いっしょに仕事して頻繁に会うようになると、オレの中にあったヒーロー像ってのが、薄れていくんじゃないかって思うこともあって。誰だってそうだと思うけど、長い時間付き合ってると馴れもでてくるし、今まで凄いと思っていたことが当たり前のようになっていくっていう状態ってあるじゃない?
── わかります。
ニール:でも、いざ目の前であのギターを弾かれると、やっぱり「凄い!」ってなるんだよ。普段、ポップコーンを食べてるときは「デヴィ爺」なんだけど、ギターを抱えると「デイヴィッド・T・ウォーカー」になるっていう凄さ。何十年も昔にハマった音が、今でもそこに存在してるってこと自体、ただひたすらひれ伏すしかないでしょうってね。いくら距離が縮まったように見えても、音楽的にはやっぱり距離があるってことなんだよね。敬意を表するっていうよりは、畏怖感というかな。これはもうどうしようもないっていう距離感なんだよね。あまりにも距離があるから、一周遅れで近くなった感じ(笑)。いろいろやってなんとか近づいた気分になってたけど、実は後ろから近づかれていたみたいな。しかも周回遅れで、距離はめちゃ遠いまま、みたいな(笑)。
── (笑)。
ニール:実はさ、やっぱり今でも自分のソロアルバムを作るってなると、デイヴィッド・Tに弾いてもらおうかって考えちゃうんだけど、そのとき思い出すんだよね、周回遅れだってことを。いつか弾いてもらいたいっていう気持ちとも違う。それよりもむしろ、デイヴィッド・Tの次のアルバムをなんとか作りたいっていう気持ちのほうが強いし。オレが関係しなくてもいいから誰か作ってよっていう。このまま彼を放っておくつもり?って。
── ホントに……そう思いますね。
ニール:彼は今でもトップギタリストだし、このまま昔の音を楽しむだけの存在にしておくのはホントにもったいない。この年になってこその円熟の極みみたいな音を出して欲しい。昔の若かった頃の音を出そうとしてもそれはもう出来ないんだよね。それよりもむしろ、若いときには出せなかった音を今こそ出して欲しい。これだけ長い間生きてきたレジェンドが作り出す今の音に対して、自分がどういうスタンスで向き合えるかっていう。好みの音かどうかは別にして、聴いてる人自身の音楽に対する意識とか立ち位置とかを再発見するにもいいと思うんだよね。
── 再発見。
ニール:これだけ長い間やってて、これだけの位置にいる人って少ないからね。例えばミック・ジャガーとかもそうなんだと思うけど、でも彼らはローリング・ストーンズっていうキャラクターを演じ続けているってところもあるわけじゃない? でもデイヴィッド・Tは違う。彼は自分のキャラクターを演じているわけでもなんでもないし、ましてや大スターという存在でもない。いつでも「デイヴィッド・T・ウォーカー」でしかないわけで。余計に彼の人生のその瞬間ってのがハッキリしてるわけ。だからこそ、この時代の今、彼が何をやってくれるのか。そこをデイヴィッド・Tのファンの人にも向き合ってもらいたいな、という想いもあるんだよね。そのときデイヴィッド・T・ウォーカーっていう人を好きになった理由もわかってくるかもしれないし、自分の音楽史の中でデイヴィッド・Tという存在がどういう位置にいるのかもわかってくるのかもしれない。
── うんうん。
ニール:若いときには年をとるってことを拒否したがるでしょ? でもホントはそう悪いもんじゃないんだよね。特にデイヴィッド・Tを見てるとそう思う。アフロヘアーで縦縞のベルボトム履いてたのが、今じゃスリーピースのスーツを着てるんだよ? なんだ?この変わりようは?って(笑)。でも、音楽に対する情熱は変わってない。年齢を重ねていくことを、ろうそくの炎が消えかかってるっていう例えを使う人がいるけど、彼の場合は消えかかっているどころか、全開で燃え続けてるんだよね。
── (笑)。
ニール:オレが今、デイヴィッド・Tに望んでるのは、音楽を続けていきながら年をとっていくことの素敵さを全面に見せてほしいな、ってことなんだよね。若い頃からスターな人って年をとってもスターでしょ? そういう人が作った音楽はいつまでもスターの音楽なんだよね。でも、デイヴィッド・Tって人は、ある意味ではスターに成り損ねた男だから。そういうところを乗り越えて、腕一本でここまで来た人だからね。そういう人の晩年が、どういう音を奏でるのか。
── 聴いてみたいですね。
ニール:今、オレがやってる音楽はエレクトロニカなんだよね。そういう音楽をやってる若い世代からすればオレなんて凄く上の世代なわけ。オッサンがこういった音楽を理解できるの?っていう感じだろうね。でも、オレにしてみれば、今までずっと聴いてきた音楽の蓄積の結果、辿り着いた音楽でもあるわけ。そこにはデイヴィッド・Tもいるし、ティモシー・シュミットやポコとかカントリーロック、そういう存在がハッキリあって凝縮されているんだよね。選んだ手段として自分一人で作るからコンピュータを使ってるんだけど、そういうことも年月を積み重ねて初めてできたわけで。そういう年月の重ね方をデイヴィッド・Tという人もまさに体現してると思うのよね。
── なるほど。
ニール:今、彼から出てくる音が、お年寄りのリラックスした音になるのか、妙に尖った音になるのかはわからない。だから聴いてみたいって思う。ぜひみんなにも後押ししてもらいたいなと。決して過去の人じゃないってことは声を大にして言っておきたいんだよね。
── 全く同感です。ここでやらねばいつやるの、と。
ニール:デイヴィッド・Tのアルバムは、いつも3枚作ってやめるってパターンなのよ。60年代も70年代も80年代も90年代も。
── ホントだ(笑)。
ニール:だから、今度新作できたら、きっとその後2枚は出せるよ(笑)。好きでいてくれる人がいて、そういう人たちが「聴きたい」って思ってくれている限りは、デイヴィッド・Tは「作りたい」って思う人なんだよね。ま、たとえ聴きたいという人がいなくなっても、ギターを弾いてるハズだよ、きっと(笑)。
(2006年10月 ロサンゼルス・ご自宅にて)
その音色の魅力に取り付かれた人は言う。「どんなふうにこの個性が出来上がったのか」。クチを揃えて語られるその興味が、20年前に一人の日本人を動かした。
ロマンティック。デイヴィッド・Tのギターの魅力をそう表現する人は多い。聴く者の琴線を直感的な刺激で揺さぶる艶やかで甘いトーンを端的に表現した言葉だからだ。美しく響く弦の音色。文字通りロマンティックなイメージを喚起しやすいその音色は、ギターという弦楽器の特徴的な側面が際立った結果でもある。そのプリミティブな感覚は、数ある表現の中から、僕らが音楽というカタチに惹き付けられる理由とシンプルに結びついている。
聴けば聴く程、知れば知る程、深い底なし沼の存在を認めてしまう魅力。次第に興味は敬意に変り、互いの距離も縮まっていく。懐の深さに見守られ、その視線を感じ取ったからこそ、適度な距離を保った関係は築かれた。周回遅れという謙虚さは、実感として出た言葉。その瞬間をわかち合った関係は、恋人でも友人でもない世界。変な意味ではなく、そこにあるのは音楽というカタチを選んだ者の澄んだ深みだ。
酸いも甘いも。時に想像を絶する経験を人は積む。それでもそこに音楽はあった。どんなに過酷な状況でもそれだけは自らが選び取った感覚と意志。そのベクトルがいかなる方向であっても、存在を認めあえる関係がそこにあった。優しい眼差しが確かにあった。
僕らが音楽を選ぶ理由。音楽に魅せられる理由。デイヴィッド・T・ウォーカーという巨人に、日本人で最も肉薄した男が実感する距離感と絆。答えはそこに揃っている。そしてそれはとてもロマンティックだ。
(聞き手・文 ウエヤマシュウジ)
ニール・オダ(にーる・おだ)
1957年8月24日生まれ。東京都世田谷区出身。アマチュア・バンドのドラマーとしてスタートし、その後、渋谷の輸入盤店店員、レコード卸業を経て70年代後半より、日本屈指のシンセサイザー・プログラマー浦田恵司氏に師事し、荒井由美、竹内まりや、エポ、尾崎亜美、矢沢永吉、寺尾聡等のレコーディング、ツアーに参加。80年代前半からは音楽評論家として「Jazz Life」「ADLIB」、日本経済新聞等で執筆。1986年からはDavid T. Walkerと共にPress On Productionを設立してプロデューサーとして活動。その他、Alex Acuna & The Unknowns、Nick De Caro、Sea Wind、Bebel Gilberto、アンリ菅野、阿川泰子、飯島真理など多くのプロデュースを手がける。90年代初頭からL.A.に定住、ミュージシャン・コンポーサーとして活動を始め、1999年にはThe John Lennon Songwriting ContestのJazz部門に入賞。これをきっかけに2000年には初のソロ・アルバム『Eclipsing The Past』をUltralights名義でアメリカにてリリース、続いてカナダ、イタリア、ドイツ、イギリス、フランス、スウェーデン、香港、台湾でもリリースされた。ボブ・ジラルディ監督の映画『ディナー・ラッシュ』をはじめ、米NBC−TVのドラマ等にも音楽を提供。Ultralightsの同僚で友人の画家/フラッシュ・アニメーターの光瀬直毅氏の多くの作品の音楽も手がけ、ヨーロッパでは賞を受賞。まもなく中世音楽とエレクトロニカをミックスしたセカンド・ソロアルバム『Ark Of The Universe』をリリース予定。またL.A.のカントリー・ロック・バンド「Running Kind」のドラマー/マンドリン・プレイヤーとしてライヴ活動もしている。さらにPoco、Richie Furay、Eagles、Chris Hillman等のプロモーションのヘルプ、ジャズやロックのコレクターズCDをオンラインで販売するなど、Sunday Mitsuru、Funky Tonk Harrie、Mitsuru "Neil" Fukasawa、そしてNeil Odaと各種の名義で幅広く音楽活動中。

|
Ultralights
『Eclipsing The Past』('00)
Shadow Records SDWO-79-2
|
|
|
|